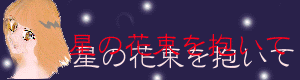 |
| 星の花束を抱いて外伝2 前奏・・・『狂想曲より』 |
| 第1章・・・すずろ |
今からそう、十五年程前に話はさかのぼる。
「ん?なんか、言った?」
昇降口の掃除を終えて、教室に戻ってきた丁度その時、自分の名前を耳にして、ふと、立ち止まる。
「あっ、気にしないで、こいつ、頭おかしいんだ。」
出入り口付近で立ち話をしていた男の子のうちの一人が言う。
「ふーん」
ちょっと、腑に落ちないままその場を立去ろうと、1歩、足を踏み出したときだった。
先ほどの男の子が
「お前が野原先輩に勝てるわけ無いだろう。」
と、もう一人の男の子に小声でささやいた。
「だめ、かなぁ。」
と、つぶやいてその男の子は俯く。
私は足を止め、二人のほうに振り返った。そして、俯いている彼の前髪を思いっきり掻き上げた。
「加月君、こんなに綺麗な顔しているのになんで、いつも前髪で隠しているの?」
そう、彼には美少年という言葉がぴったりはまる。
切れ長の眼、真っ直ぐな鼻梁、尖った顎・・・その顔をいつも服装規定で引っかかる長い髪で隠している。
「私、加月君のこと、裕ちゃんと比べたことなんて、無いよ。加月君は加月君でしょ。もっと、胸張って良いと思うけど。」
彼は自分の髪をつかんでいる私の右手を、左手で引き剥がした。
「じゃぁ、」
俯いた顔を上に上げた。
「デートして。」
突然の申し出だった。まぁ、少しは予期していたけど。
「いいよ。ディズニーランドに連れて行ってくれる?」
にっこり、微笑んでみた。
私はそのまま自分の席に戻ってカバンに教科書を仕舞い始めた。
「織方さん、廊下で裕二さん、待ってる。」
加月君がまだ、さっきの場所にいて私を呼んだ。ちょっと複雑な表情を浮かべて。
「あっ、サンキュ。」
カバンを抱えて廊下に飛び出す。
「遅いっ。」
一応、そう、言ってみる。
「ごめん、ヤボ用。」
一応、言い訳される。
「そうそう、」
私は教室を振り返る。
「加月君、今夜、電話するね。」
そう、言い残して、私は裕二と並んで階段を降りて行った。
彼、『野原 裕二』は、私の幼なじみ。二つ年上の高校3年。そして去年の夏スクリーンデビューを果たした俳優でもある。まぁ、簡単な話、スカウトされたのだった。
裕二はどちらかと言えば女顔の美形。とっても大きな瞳、長いまつげ、ぷっくりと厚い唇・・・整った顔だ。
どうして俳優になったかって聞いたら、
「金、稼げそうだから。失敗したら次を考えるよ。」
と、平然とした顔で答えた。
そんなことを考えながら歩いていたら、裕二が怪訝な顔をして私の名前を呼んだ。
「あき、俺と一緒にいても、つまんなそうだな。」
「そんなことないよ、今だって裕ちゃんのこと考えてたんだから。」
そう言って、腕を組んだ。
裕二が立ち止まって私を抱きしめる、そして、そっと唇を重ねた。
私は慌てて裕二から離れる。
「人に見られちゃうよ。」
多分、赤面してたと思う、顔が熱かったから。
「いいよ、俺達婚約したじゃないか。来年の3月には結婚するんだから。」
そう、私達はもう2年も前に親の承諾を得て婚約した。
裕二が高校を卒業して、私が16歳になったら結婚しようと約束している。
3月30日、私の誕生日に結婚式を挙げる予定なのだ。
「結婚したら一緒に暮らすんだ。何にも、問題は無いだろう?」
「だめだよ、裕ちゃん有名人だもの、何言われるか分からない。」
「涼だっていずれその『有名人』になるんだぞ。・・・多分。」
憮然とした表情。
「涼?」
「さっき、あきがデートの約束していた、加月 涼。」
「あっ、加月君って涼って名前だったの?知らなかった。で、加月君がどうした・・・もしかして、裕ちゃん妬いてるの?」
「めちゃくちゃ、嫉妬してる。あきが、俺の知らないところで他の男に口説かれてるなんて、やだな。」
そう言って、裕二はさっきよりも力をこめて私を抱きしめ、唇を重ねた。そして、そっと、舌を差しこんできた。ぎこちないディープ・キス。それでも私は頭の中が真っ白になってしまった。
「ディズニーランド、俺が連れて行ってやるから、断れよ、涼とのデート。あきは俺のことだけ考えてて。」
私は裕二の首に両腕を回し、そっと耳元で
「大好きだよ、裕ちゃん。」
と、ささやいた。
「でも、今回だけは良いでしょ、お願い、ね。」
わざと、甘えた声で言う。
分かっていてやった、彼が私のわがままを許してくれること。
今考えると、どうしてこんなに加月君とのデートにこだわったのかが分かるけど、あのときは、不思議だった。
そして、どうして裕二が行かせたがらなかったのか・・・。
「じゃあ、交換条件。俺達のこと、公にしていい?お前のことは、俺が守ってやるから。」
もう一度裕二とキスをした。
「愛してる」
裕二は何度も、そう、言った。
日曜日、駅の改札口で加月君は、待っていた。
10分の遅刻。
今朝になって着て行く服を迷い始めて結局遅刻してしまった。
でも、そうとは言えないので
「寝坊した。」
と言ってしまった。
言った後に
「緊張して夕べなかなか寝付けなかったから。」
と、付け加えた。
「ねえ、加月君、『涼ちゃん』って、呼んでいい?今日はデートだし。私も名前で呼んでね。」
可笑しいくらい私ははしゃいでいた。
多分それは加月君・・・彼も気づいていたと思う。
彼も私も遊園地に行くのは久し振りだった。
延々と続く長い列に並ぶのもちっとも苦にならなかった。何故だろう。彼とはもう、何年も一緒にいるみたいな、そんな気になってしまう。
「裕ちゃんが言ってたんだけど、同じプロダクションにいるんだって? 知らなかった、いつからなの?」
「裕二さんとね、ほとんど同時期なんだ。彼のほうがちょっとだけ早い、のかな。それに・・・。」
ちょっと、口篭もる。彼はどうも上手く言葉にならないらしい。私は黙って、待っていた。
「僕達、だめ、かもしれない。」
「僕達?」
再び口篭もる。辛抱強く、待つ。
「…デビュー出来ないと、思う。だって、メンバー同士の意見が合わない。このままじゃ解散、しなきゃいけなくなる。」
私は頭の中でぐるぐると彼の言葉をシェイクする。そして一つの答えを導き出す。
「涼ちゃんのパートは?」
「ボーカル」
ん、やっぱりバンドか。咄嗟には言葉が出なかった。でも、彼にはボーカルが似合うと思った。バンドの花形。さっきから何人の人が彼に振り返ったことか。
「音楽の授業、とってないよね。歌、聴いたこと無いよ、今年は文化祭の無い年だし、つまんない。」
「聴きたい?僕の歌。だったら頑張るよ。」
今までで1番うれしそうな顔をした。
「歌、好きなんだ、ずっと、子供の頃から。」
ぽつりぽつりと、自分のことを話す。
小学生の頃から沢山の歌を作ったこと、中学1年でバンドを組んだこと、いまのバンドは3つ目のバンドでプロを目指していたけど最初はアイドルにされそうだったこと。
「プロダクションに所属しているって言っても、本当に名前、登録しているだけ。」
照れくさそうに、笑った。
「でも、織方さんが応援してくれるなら頑張るよ。」
「うん、私涼ちゃんのファンクラブ、作っちゃおう。」
どんどん彼の顔が赤くなって行く、
「いいよ、恥ずかしいから。」
と、言いながら。
帰り道、彼はやっぱり黙って、私の話を楽しそうに聞いてくれた。
大丈夫だと言うのに
「心配だから。」
と言って、家の前まで送ってくれた。
「今日は、ありがとう、僕のわがまま聞いてくれて。もう、こんなこと、言わないよ。裕二さんに、悪いから。」
寂しそうな瞳で、でも、ちょっと怒ったような口調で、そう言って、彼は走り去った。
(なんで、ここで裕ちゃんが出てくるの?)
私は彼の後姿をずっと見送っていた。後姿が見えなくなって、しばらくしてから、家に入ろうと180度身体を回転させたときだった。左腕を力いっぱい引っ張られた。
「裕ちゃん!」
(涼ちゃんは気づいていたの?裕ちゃんがここに居たこと・・・)
だから・・・。
黙って私を引っ張る。そのまま裕二の家に入る。
「涼に何された?」
「何も、ないよ。」
「嘘だ。」
「嘘言ってどうするのよ。」
私は裕二を睨み付けた。
「…もう、やだ。もう、待てない。」
そのまま、階段を上がって、裕二の部屋に連れて行かれた。
ドアを後ろ手に閉めながら、
「あきらが、欲しい。いいだろ?」
そうか、そういう、ことなんだね。大丈夫私、覚悟はしていたから。
でも、なぜ、今日なのだろう。それでも、拒否できない。
多分、
『どうして今日は嫌なのか。』
と、聞かれるから。
「いい、よ。」
私は少し俯く。
「後悔させないから。必ず幸せに、するから。」
抱きしめられて、キスをして・・・。
「好き・・・、裕・・ちゃん・・・」
言い訳の様にささやく。だって、私、裕二の腕の中で、涼の寂しそうな瞳を思い出していた、から。
同い年なのに大人びた表情を、する。時々前髪を無造作に掻き上げる。動くたびに揺れる、肩まで伸びた長い髪。
一つ一つのことが、新鮮に私の目に飛び込んでくる。
翌日、気がつくと私は「加月 涼」を目で追っていた。
なのに、声が掛けられない。昨日のお礼が言いたいのに。
目が合ったとき、思わずそらしてしまった。
そして私はまた、寂しそうな瞳を見てしまった。この間までの彼と同じように私は俯いたまま、何も言えず帰宅した。
火曜日の朝だった。
長かった髪をばっさりと切り、前髪も短くなった、彼がいた。
そう、本当の彼は意思の強そうな光を放つ瞳を持った人だった。知っていた、そんなこと。
寂しげな瞳にしたのは、私。
その瞳がストレートに私の目に映る。
私なんか、変だよ。
ゆっくりと、彼が私のところにやってきた。
心臓の鼓動が大きくなる。
少し、ためらうように、でも、しっかりと私の目を見て、言った。
「…デートしてくれたんだったら、その日くらい…その日1日くらい…僕のこと考えて欲しかった…。」
私は目を逸らした。
「昨日裕二さんに会った。うれしそうに話していたよ。」
それだけで十分だった。奥歯を力いっぱいかみ締めて、涙をこらえた。でも、無駄だった。
「ごめん…ごめんなさい。」
それだけ言うのが精一杯だった。彼の視界の中にいるのが辛かった。逃げたかった。
ごめん、裕ちゃん、私、彼が好き。気づいちゃった。だから、後悔している、あなたに抱かれたこと。
予鈴が鳴った。次の授業がはじまる。
でも私は居たたまれなくて教室を飛び出した。
「ちょっと、待って。」
彼が追いかけてきた。屋上につながる階段の踊り場で肩を掴れた。
「ごめん…でも、好きなんだ、君のこと。」
「ちがう…の…」
彼に背を向けたまま言った。
「加月君…違うの…ごめんね。」
言えない、今彼に裕二とセックスしたことを言われたばかりなのに…。
彼が戸惑いながら、そっと、後ろから私を抱きしめた。
「…好きでいて、いい?今まで通り、片思いでいいから…嫌わないで…。」
「…お願い…私に触らないで…。」
慌てて彼は私から手を離した。
「ごめん、もう、遅かったね。」
「私、あなたに好かれる資格が無いの。だって、裕ちゃんと…」
「織方さんは、織方さんだろ。何が変わったの?僕は、好きだよ。」
あぁ、私の好きなこの瞳が揺れている。この時の私ほど、誠実でいて、不誠実だったことは、ない。
この人を泣かせたくない、裕二と引き換えにしても、良い。
「…好き…」
私は堪え切れなくなって、言っていた。
「うん」
俯いたまま彼は頷いた。自分の気持ちを繰り返されたのだと思ったのだろうか。
「加月君が好き。」
「え?」
視線が交錯する。
「日曜日から涼ちゃんのこと考えないときが無いの、朝も昼も夜も・・・裕ちゃんといる時も。」
先に目を逸らしたのは彼のほうだった。
「・・・だって・・・」
彼の右手が私の左の頬に置かれた。
「君は、裕二さんの婚約者で、僕は片思いで・・・本当は忘れるつもりだった。デートしてもらったからそれでいいと思っていた。なのに、そんなこと言われたら・・・。」
(今日は、一杯話してくれるんだね・・・。)
そう思いながら、目を、閉じた。ほんの一瞬、唇を重ねた。
「もう、離せなくなっちゃうよ。」
痛いくらい抱きしめられた。
「本当に、僕で、いいの?」
「うん、加月君がいい。」
−私、その瞳が好きなの。裕ちゃんごめんね、私、加月君が好き。
もう、この気持ち止まらないの。 |
| 第2章・・・つらみ |
裕二が小学校6年のときだった。
日曜日の夕方、家の前にたたずんでいるあきらに会った。
「どうした?」
「パパとママが喧嘩してるの。パパ、すっごく怖い顔しててね・・・」
いつもの夫婦喧嘩。知っている、ここの夫婦はしょっちゅう喧嘩している。
言っている間にあきらの母親が飛び出してきた。
「あきらっ、おばあちゃんの家に行くよっ。」
「やだっ、 あきら、裕ちゃんと一緒に遊ぶんだもの。ね、裕ちゃん。」
あきらのささやかな抵抗。
裕二には兄と姉が一人づついる。けど、皆年が離れているので、なんとなく遠慮していた。
だから、隣に住んでいるあきらがとっても可愛くて仕方なかった。そう、あくまであきらは『妹』の存在。
「いいよ、おばちゃん、行って来て。あきらは僕が見ててあげるよ。」
どうせまたすぐ帰ってくる。そんなこと、あきらも裕二もお見通し。もちろんあきらの父親だってお見通し。だから追いかけてこない。
「・・・そっ、じゃあね、ばいばい。」
そう言ってあきらの母親は駅に向かって歩いて行く。
「なにして遊ぶ?」
「んーっとねぇ・・・」
それでも瞳は母親を追いかけている。
「駅まで迎えに行こうか。」
「うん。」
小さな手が僕の手に必死にしがみ付く。
「大丈夫だよ。いつも、帰ってくるだろ。」
「・・・う・・・ん・・・」
しかし、その日、あきらの母親は帰ってこなかった。
「何かあったら僕が守ってあげる。あきらには僕がついててあげるから。」
すがるような瞳と、小さな手。そう、この日から裕二にとってあきらは『特別』になった。
切ないくらい裕二の片思いだった。何年たってもあきらにとって裕二は幼なじみ以上にはならなかった。
中学生になった頃クラスメートには「恋人」って、言いふらしていたらしいが、裕二の前ではそんな素振りは見せない。
ただ、学校で人気の有る裕二を独占できる優越感に浸っている、という感じだった。
あきらは美人じゃ、ない。でもどこか人を惹き付ける魅力の有る女の子だ。可愛らしい−という言葉がぴったりはまる、そんな子だった。
明るさだけは天下一品かもしれない。
いつも笑っている、そして、いつも何か話している。
「あき、今度の日曜日デート、しよう。」
裕二はあきらのことを「あき」と呼ぶ。そうやって、あきらに特別意識を植えこんでいるのだが・・・。
「なに、突然改まって。」
「たまには良いだろ?ちゃんと待ち合わせして、デートして・・・。」
そして、ちゃんと自分の気持ちを伝えて、あきらの気持ちも聞きたい。
結局家まで迎えに行った。映画の時間に間に合わなくなって、一回見送ることにした。
「前売り買ったんだから、絶対見る。」
裕二は予定通りいかなくなって、ちょっと困っていたけど、順番を逆にすることに、した。つまり、先に『告白』することにした。ちょっと、緊張。
「 あき、あのさ・・・」
ウィンドーショッピングしながら言う台詞・・・じゃないな。そう思って、手をつないだ。
あきらは裕二の手を、握り返した。たまらなく愛しかった。
「好き、だよ。」
耳元で、小さな声で、言った。
「うん、私も。」
正面を向いたまま少し俯いて、そう、言った。
・・・人目が無かったらきっと抱きしめていた。
もう毎日毎日、頭の中はあきらのことばっかりだった。
誰にも渡したくなくて、戸惑う両親を説き伏せて『婚約』して。
婚約するにはそれなりの覚悟があったわけで。
それで『俳優』なんて職業を選んだ。
何でも良かった。
あきらと二人の生活が出来るならどんな仕事でも良かった。
高校卒業して、法律が許してくれるあきらの16歳の誕生日。
その日が結婚記念日に、なる。
その日は1日中、嫉妬で気が狂いそうだった。
涼が、あきらを好きだったなんて知らなかった。知ってたらもっと早くに手を打っていたのに、どうして・・・。
涼とはよくレッスン室で一緒になった。二人とも素人なのでボイストレーニングは必須だった。
あきらの話は沢山したような気がする。あの時は誰かに話したくて、うずうずしていた。今ごろ後悔しても遅い。
顔を見れば良かった、それだけで気が済むはずだった。なのに、どうしても自分の物っていう確信が欲しくなった・・・。
翌日のレッスン室で涼に会った。
「昨日、あきらに何かしただろう?」
思いきって牽制球を投げることにした、今更遅いけど。
「・・・してませんっ。」
はっきり言われた。
「いいんだ、俺が、何かしたから。」
ちらり、と、涼の顔を見る。堅く目を閉じている。
「涼が帰ったあと、あきらとセックスした。」
顔を真っ赤にして今にも泣き出しそうな顔で、首を左右に振りながら
「裕二さん、意地悪しないでよ、僕の・・・片思い・・・なんだから。」
苦しそうにそう、言った。
「そっくりそのまま、その台詞お前に返すよ。」
吐き捨てるように言って部屋を出た。
――そうだよ、あきらは俺に恋なんてしていない、恋した気になっているだけ。ただの、幼なじみの延長線上に居るだけ。
だから焦っているんだ、だからセックスしたかった、俺のものにしたかった・・・。
自分以外の人間のいない世界に隠してしまいたい、だめだったら涼だけで良いよ。
俺の腕の中で、あきらは涼の名前を呼んでいた、はっきりとは聞こえなかったけど、あれは、「涼」だった――
「やだ・・・。俺はあきと、結婚するんだ。」
――ナニ、言ッテンダヨ。――
心の中でもう一人の自分が言う。
「誰にも渡さない、あきは俺のものだ。」
――早スギルヨ・・・。
「俺の何がだめで、涼の何がいいんだ?」
――マダ恋シタバッカリダロ?涼ニ・・・何デ気ヅイチャウンダヨ。――
分かっていた、もう、戻れないこと。心の中で大きく一つため息をついた。
「・・・あきが俺のこと愛してくれるの、ずっとずっと待っていた。努力だってしたつもりだよ。足りないって言うならもっともっと努力するから。だから・・・」
――捨てないで・・・。――
この一言が言えたなら・・・。
「ごめんなさい。」
あきらが言った言葉は、予想していた通りだった。
「裕ちゃんを想う気持ちと、違うの。裕ちゃんのこと好きだけど、涼ちゃんを想う気持ちが止まらないの。」
分かるよ、目が違う、そんなに瞳を輝かしているあきら、見たこと無いから。
「俺の手を離したこと、後悔するから。あきらを本当に愛して、幸せに出来るのは俺だって、気づいたら帰っておいで。」
帰ってくるわけなんか、無い。分かっているけど、最後の悪あがき。
身を切る想いって、こんな感じなんだろうな・・・そんなこと、考えていた。
他のこと考えないと涙が出そうだった。
でも、だめだった。
地位も名声も、親も兄弟も、なにも、いらない。
あきらだけでよかった。
欲しかったのはたったひとつだったのに・・・。 |
| 第3章・・・たぐふ |
「そっか、良かったね。」
あきらは心にも無いことを口にする。
「本当にそう思ってる?」
・・・分かっているなら、言わないで欲しい。
「・・・ううん・・・だって、デートできなくなっちゃう。」
出来ればずっと、ずっと側にいたい。
「止めちゃおうか。」
あきらは視線を外した。
「本当に?」
自分でも分かるくらい声音が変ってしまっていた。
「ごめん・・・そんなことできない・・・」
今度は涼が視線を落とす。
「わかってるよぉ、だから、わざと言った。」
だって、『夢』だもんね。
涼とあきらが付き合い始めてそろそろ1年になろうとしていた。
涼にとってはそれこそ慌しい1年だった。
夢がいくつも転がり落ちてきた。あきらとのこともそうだったが、あんなに意見の合わなかったバンド活動が急に軌道に乗り始めた。
新曲作り、音合わせ、そしてライブハウスでの活動。
何度もデートの最終地がライブハウスになった。
ほんの3ヶ月ほど前、レコード会社が決まり、何曲かレコーディングした。いよいよ、デビューが決まったのだった。
「・・・親父が、九州に転勤するんだ。そうしたら家に、来ない?一緒に暮らしたいって、思っているんだけど。」
相変わらず伏目勝ちに話す。
「だめだよ、私達高校生だよ。」
「裕二さんとは結婚するつもりだったくせに。」
涼は裕二に嫉妬しているのだ、だからつい口調があきらを責めるようになる。
「あれは・・・」
「いやなんでしょ、家にいるの。ばれないって、大丈夫だよ。」
学校でそんな話したって説得力無い――と思ったが黙っていた。
「考えといて。」
2年になって、クラスが分かれてしまったので、昼休みにしか会えないけど、必ず涼はあきらの前に顔を出した。
考えることなんて何も無い、今は涼と一緒にいたい・・・それがあきらの答え。
あきらは黙って家を出てきた。多分すぐにここに居る事気づかれてしまう、でも一緒にいたかった。
裕二との婚約を破棄したこと、やっぱり後ろめたくて、家に居るのはいたたまれなかった。
涼はちゃんと両親に認めてもらえる交際がしたい、何て言うし。
「他に行くところないよ。」
そう言って涼に甘える。
「さっき、お母さんから電話があった。」
「なんだって?」
「勘当だって。」
「そうかぁ。」
「嘘っ、嘘だよ、『ちゃんと責任取りますから』っていったら笑われちゃったよ。」
「そんなこと、言ったの?」
恥ずかしいじゃない。
「でも、一緒に居られる。」
「うん」
視線を合わせる。あきらは目を閉じる、それに答えて涼が唇を重ねる。
決して涼からはキスを求めてこない。それがあきらには不服であった、けど、涼に夢中になる原因でもあるから非難もできなくてもどかしかった。
涼の欠席日数が増えてきていた。
最初は学校が引けてすぐに飛んで行っていた。
しかし、状況が状況だけにしばらくは欠席が続くようだ。家にも余り帰ってこない。徹夜が多いのだろうか・・・。
結局涼の家に来たと言っても、一緒にいたのは1ヶ月の4分の一、つまり1週間。
昼間、帰ってくることが多いようだ。
着替えてまた出かける、そんな感じらしい。実際に会っていないから分からない。
元気なのは分かる、メモが残っているから。
そして今日は帰ってくるって書いてあった。
得意な料理なんてあまりないのになぁ・・・考えながら台所に立つ、もう、ほとんどレパートリーは出し尽くした。
ご飯炊いて、ワカメとお豆腐のお味噌汁、肉じゃが、サラダもつけよう。
涼からもらった生活費・・・涼の両親が毎月送ってくれるのだけど、それでも、嬉しかった。母からも少しお金貰ったし、苦しいことは、何も無い。
―私、涼のこと待ってても良いってことよね。―
カチャッ
玄関の鍵の開く音がした。あきらが飛び出してきた。
「・・・ただいま。」
「お帰りなさい。」
二人とも照れくさそうに、笑う。
「夕食のしたく、まだ途中なの。さき、お風呂入ってて。」
「ん。・・・なんか・・・。」
涼は言いかけて止めた。
「風呂入ってくる。」
涼が一緒の家の中に居て、自分の作った料理を食べてくれる。
涼は口下手で純情だからそれ以上なんて無理だよね・・・。
なのに、ものすごい力であきらは突然後ろから抱きすくめられた。
髪に鼻を埋めて、
「髪、伸びたね。」
なんて、優しい声でささやかれた。
「うん・・・、涼が好きでしょ、長い髪。」
「会いたかった。」
頭をぐっと掴れてそのままむさぼるようにくちづけを、した。
―こうして、どんどん涼に夢中になっていくんだなぁ―
ぼんやりとした頭で考えていた。
「今度こそ風呂入ってくるよ。」
笑顔でバスルームに消えて行った。
「涼、一緒に寝て良い?」
あきらにとっては重大な決意だった。
バスタオル1枚だけ身体に巻いて涼の部屋に来た。
「ど・どうしちゃったんだよ。そりゃ、責任取るって言ったけど。」
「だって、涼、たまにしか帰ってこないし・・・寂しいよ。ね、お願い。」
「・・・買って、ないんだ、コンドーム・・・」
「いらない、涼の赤ちゃん、欲しい。」
―だって、黙っていたらずっと涼は抱いてくれない。
そしていつか有名人になって私のことなんてどうでも良くなってしまう。そんなの嫌だよ、こんなに、こんなに涼のこと好きになっているのに。
―涼はもう何も言わなかった、黙ったままあきらを抱きしめた。
そして長い長いディープ・キス。
そっとあきらを包んでいたバスタオルを身体から外し、ベットに横たえた。
「僕はさ、Hだから一回やっちゃうと毎日したくなっちゃうよ、それでもいい?」
照れて笑う。
返事の代わりにあきらは微笑んだ。
翌年の夏、涼がライブツアーに行っている最中、『零』は産まれた。元気な男の子だった。
「結婚」は、隠しておけそうだったけど、「出産」となると、話は別。私も涼も学校を辞めていた。学校より私には『零』が大切だった。
後で聞いたら出産日、涼の歌はめちゃくちゃだったそうだ。歌詞は忘れる、音程はずれる。
「産まれたら連絡する」
と、母に言われていたのに、私には目に浮かんでしまった、涼の動揺ぶり。
翌日病院へ飛んできて、
「名前は『零』って、決めたから。」
嬉しそうにはしゃいでいた。
「来年はツアーに引っかからないときを選ぼう。」
なんて・・・。
『零』・・・何も無い二人から産まれた子だから、『零』 |
| 第4章・・・ながる |
「夢、見た。」
涼の一言。
「裕二さんが『あきらを返して』って。泣いていた。」
涼、それ夢じゃないね?
約束どおり、零を産んだ翌年『実紅』を産んだ、今度は女の子。そして先日『夾』が産まれた。
涼は一人っ子だったから兄弟は沢山作ってあげたいと言う、けど・・・。
実紅の時は零一人だったから、母に手伝いに来てもらったのだけれど、夾の時は小さい子供二人抱えて・・・というのはあまりにも大変だったので、実家に戻って出産した。
孫が出来たら両親も喧嘩をしなくなり、二人で零と実紅を取替えながら面倒を見てくれるのでつい、甘えてしまった。
2ヶ月近くも家を空けていて、明日には帰ろうと、思っていた。
――見覚えの有る天井、でも、もう、ずっと見ていなかった。頭がボーっとしている。
「気がついた?」
懐かしい、声。そう、これは・・・。
私は身体を起こした。ここは、裕二の部屋だ。
私はベットの上に寝かされていた。
腰まで伸びた長い髪、すらりと伸びた指、華奢な首・・・でも以前のような優しい瞳は無くなっていた。
「クロロホルムってホント良く効くんだ。ドラマとかで言ってて半信半疑だったんだけどね。・・・仕事、ばっくれちゃったよ。もう、だめかもなぁ。」
楽しげに話すことじゃ、無いよ。
「お願いがあるんだ。聞いてくれる?」
ドアを背にして出口を封鎖しながら言う。
「一人だけで良いんだ。・・・俺の子供、産んでよ。」
光の無い瞳が私を見る。
「俺が大事に育てるから、一人で育てて行くから。産んでくれるだけで良い。」
「そんな勝手なこと。」
鋭い眼光を私に向け、大股で歩み寄る。そして、私の言葉を封じた。
「今だけ、俺を見て、身体を預けて、お願いだから。」
スカートの下へ手を入れられた。
「いや・・・やめて。」
裕二は力づくで私を押し倒し、下着を毟り取った。
「・・・4年、待ったんだ。」
Tシャツを胸までたくし上げられブラジャーを押し上げられた。
この時私は「犯される」ことより「産後の身体を見られる」ことが嫌だった。
裕二には綺麗な身体を覚えていて欲しかった。
「私、結婚したのよ、3人の子供がいるのよ。」
「わかってる。でも・・・愛してる・・・」
もう、裕二の行為を止める気力が、私には無かった。
裕二は私の中で射精して果てた。
「今でも、愛しているんだ、お前しか見えないんだ。側にいて欲しいなんてもう、言わない。俺の女はお前だけだって思うくらいいいだろう?これから先、誰ともセックスしない。これが最後って
決めたから。だから、もしも出来たら産んで。俺とあきらの子供。」
裕二は私から身体を離した。
「見てよ、あきらとの約束。ちゃんと守っているだろう?」
そう言って長い髪を掻き上げた。
「私、涼を愛しているの。裏切れない。」
「俺が涼に話すから。」
床に散らばった下着と服を身に着け、私は裕二に背を向けた。
4年の間、ただ悶々と過ごしていたわけじゃ、ない。
俺の腕の中からするりと抜け出してしまったあきらを遠くから見つめていただけじゃない。
・・・外から見れば華やかに見える芸能界に身を投じたのも全てあきらのためだった。
一刻も早くあきらの全てを自分のものにしたくて、意味もわからない『科白』を口にしてきた。
なのに・・・。
『仕事』が入ると忙しくなる。
朝から『ロケーション』とかあったり、『スタジオ』で撮影があっても深夜に至ったりなんてざらだった。
でも、撮影が終わってしまうと、ぽっかりと時間が空いてしまう。
『転職』しようと思っていた。今の仕事にずっと縋りついている気持ちは全然無かったから。
あきらが側にいてくれたら平凡で、ため息の出るくらい平凡な生活をしようと思っていたから躊躇わずに高校から大学へ進学した。
悪いけど、俺は成績良かったからね、誰にも文句は言えなかっただろう、そして今だって誰にも何も言えないだけの成績を残している。
大体大学の単位なんて馬鹿げている。
講義の始まる前に出欠とって返事が聞こえればいいのだから。
試験だって、『ノート』『教科書』持込可、なんてのが普通で持ち込めない物だけ『暗記』すればいいのだから。
つまらない教授の話を聞いてやって、無駄な90分をやり過ごす。そして4年経ったら『優秀な成績』で卒業してあげるよ。
仕事を続けながらひとつも単位を落とさないでやって来た。たとえ『結婚』してたって自信はあったんだ。
・・・これじゃ、未練たらたらだよな。
確かに涼にあきらを奪われたって思っているから、いつまでたっても彼女の気持ちは俺の上にあると信じていた。
しかしそんなささやかな希望も、1年しかもたなかった。。
あきらの部屋に電気が灯らなくなった。毎日毎日、暗いままの窓。両親はあきらを恨んでいる――と、いうのは正しくないな、俺のために関係を持たないようにしてくれていただけだろう、だから
あきらの行方なんて知らない。
あきらの両親になんて、聞けない。そんな惨めなことプライドが許さない。そして、もちろん『涼』に聞くことも。
あぁ、そうか、あきらは涼と一緒にいるんだ・・・そんなこと、そんな簡単な答えに辿りつけないほど動揺していた。
そして・・・やっと気付いた――もう、あきらをこの腕のなかに抱くことも、取り戻すことも、不可能だということに。
まず、一番手っ取り早いのは『大学』の女の子に声を掛ける事だろうな。でも嫌だった。知り合いが多いから。
で、次に考えた――共演した、女優・・・
やって見たら簡単だった、親から小遣いを貰うのよりも(もう、貰ってないけどさ)簡単に、落ちた。女優っていうのは『高嶺の花』って思われているから声が掛からないんだそうだ、だから職場結婚
よろしくぽこぽこと、『大物俳優』と『大物女優』のカップルができちゃったり、する。
あきらの時みたいに外で会ったり出来なかった。ほら、腐っても『女優』だからさ。
で、結局相手のマンションで会うんだ、こっちは実家だから。
俺は死んでも一人暮しは嫌だったし。(一人暮らしという言葉も嫌いだ、無駄に『独り身』なのを強調されているようで・・・)
さあ、めくるめく愛の世界へダイブ・・・出来なかった。この女に魅力が無いんだと思って次々と変えてみたけど・・・だめだった。勃たない・・・俺が・・・なんで?
頭は理解しても身体が理解してくれなかった。
どうしてこんなに女々しいのだろう・・・いやだ。
切り離しても切り離しても、追いかけてくる『愛している』のひとこと。
なんで、どうして、『あきら』じゃなきゃだめなんだ?
星の数以上に彼女より綺麗で可愛くて魅力的な女の子がいるのに・・・。
あきらめた、もう、恋なんてしない、いいんだ、俺の恋は一生にひとつだけ。
その代わり地味な生活なんて、しない。
人がうらやましがるようなそんな人生を送るんだ。
・・・そんな時だった・・・。
・・・言葉に、ならなかった。瞬きもせず、母を振り返った。
「・・・どうしようかと、思ったけどね、一応耳に入れておこうと思って。・・・もう、大丈夫でしょう?」
気を使いながら話してくれる母に、感謝していた。
『あきらが、涼と結婚して・・・子供が産まれた』
そんなこと、分かっていたじゃないか。
明かりの灯らない窓を見たとき、分かったじゃないか。
涙も出なかった・・・馬鹿らしくって。
テレビ局で涼に会ったのは更に1年後、だった。
バッティングすることなんてまず無かったのにな。
大丈夫、これでも演技派なんて言われちゃってて・・・(笑うなよ)ポーカーフェイスくらい作ってやるさ。
「よっ」
「裕二さん・・・」
涼の動揺の方が大きくて、こっちまで引っ張りこまれそうだった。
「あの・・・」
「あきら、元気か?」
「はい。裕二さん、僕達、結婚したんです、裕二さんにお知らせするの遅くなっちゃって。すみません。」
「ばーか、んなこと・・・聞きたいわけ、無いだろう。」
俯いてしまった。馬鹿はこっちか。
「じゃあ。」
涼の前から逃げ出した、もう2度と会いたくない、なのに俺の願いはモノの見事に3日で裏切られた。オフィスでばったりと。
「子供がいるからあきらには近づくなって言いたいんだろ?わかってるよ、うるさいな。」
「・・・裕二さん、子供がいるからじゃ、ない。僕には彼女が必要なんだ。」
「『そして、あきらにも僕が必要だ』って、そう言うのか?・・・そんなのろけなんか、聞きたくない。」
どうして涼の目の前に俺は立っているのだろう。なにもかも、もういらない。そして、初めて涙がこぼれた。
裕二に強姦・・・ううん、違う私は納得したんだから、和姦に、なるのだろうその夜、涼が迎えに来た。
両親には明日だと時間が取れないとか言い訳していたが、裕二に会ったのだろう、顔が引きつっていた。
車の中で涼は一言も話さなかった。
家に戻って玄関のドアを開けた時だった。
「裕二さんと寝て、嬉しかった?気持ち良かった?」
色を失った瞳が身体を射抜くようにじっと見つめる。
「涼・・・っ、わたし・・・」
亮は小さく、首を振った。
「ごめん、頭じゃ分かっているけど、心がついていかなくて。あきらは、どうしたい?」
すっかり寝こんでいた子供達を手際良くベットに寝かせて、リビングに戻ってきた。
「産んで、あげたい。」
「『産みたい』のか?」
「産んであげたい、だって、裕ちゃん、子供の頃私が言った一言、覚えていて守ってくれてるの。そんなに、私のこと・・・私なんかのこと想ってくれてるのに、私何も彼にお返ししていない。」
テレビの向こうで歌う外国人を見て、同じ髪型にしてと、せがんだ。そんなつまらないこと、守っている。
「結婚の約束、破ってしまったから・・・」
「分かった。」
涼は立ちあがって受話器を握り、番号を押した。
「もしもし・・・裕二さん・・・あきらが産むって言うから、僕には止められない。でも、一人だけ、それと僕に内緒で、もう、あきらに会わないで。それだけは絶対守ってください。」
私は床に座りこんで泣いてしまった。
「まだ、分からないだろ。僕は受胎しないことを祈っている。・・・いいんだ、僕はあの人から君を取り上げたんだから。これくらい、平気だよ。」
寂しげな瞳で、笑った。
なぜ、涼を苦しめるようなことをしているのかな。
べつに、どうしても裕二の子供を産みたいわけじゃ、ない。
ただ、私の中で育っているこの命を見捨てることが、出来ない。
私が産んで上げてそれで裕二が幸せになれるなんて、自惚れてなんかいない。
逆に彼が苦労することが目に見えている。
そして涼が一番悲しむ。
・・・私だって10ヶ月お腹の中にいた子を手放すことが出来るだろうか。
なのになにかが、私を押し留める。『この子は生まれて来るべき子供』なのだと。
何度、涼に頼んで中絶しようと思ったか・・・出来なかった、そしてついに5ヶ月目に入ってしまった。
裕二のこと、好きだった。でもそれは恋じゃなかった、ごめんね、裕ちゃん、私は涼に恋をしたの。
桜の花咲く季節も、緑の風が吹く季節も、太陽が肌を焦がす季節も、山の葉を色づかせる季節も、木枯らしが吹く季節も、頬を打つ寒さの季節も、雪が舞い散る季節も、いつもいつも涼と一
緒にいたかったの。
あなたに比べたら涼は大人しくって、真面目で、つまらない人だって思うかもしれない、でも、涼とあなたの違う所は、一番違う所は『私を大事に思ってくれる、私の意見をちゃんと聞いてくれる
』こと。
裕二だって大事にしてくれたけどそれはペットの犬か猫に愛情を注ぐような、そんな感じ。
涼は必ず私にどうしたいか、聞いてくれる。そして尊重してくれる・・・今回だけはそれが重かったけど。
学校を辞めて零を産みたいと言った時だって賛成してくれた。実紅と夾の時は涼が欲しがったんだけどね。
こんな風に私達は自分達の生活を確立していたのに。
「どうしたの?なんか、元気無いね。」
夕餉の席で涼が微笑む。
「涼・・・私・・・産みたく、無い。」
とたんに涼の顔が曇る。
「なんで、今頃・・・」
「私・・・こんな、嫌な女で・・・涼・・・苦しめてばっかりで・・・」
「あきら、君は勘違いしている。僕は苦しんでなんか、いない。」
毅然とした口調だった。
「そりゃあ、裕二さんが君を抱いたって聞いたときはショックだった、でも、僕だったらどうなんだろうって考えた。・・・裕二さんが君のことまだ好きなの知ってて実家に帰して、毎日零と実紅の声が
聞こえて、夾が泣く声がして。どうにかしたいって気持ち、分かるから。僕だって好きだったから裕二さんの婚約者をデートに誘っただろ。もっと早くに迎えに行かなかった僕の責任だ。それに、宿
った命を殺すようなそんなあきらだったら・・・離婚してる。望まれた子供だ、産んであげようよ、僕には3人子供がいるから、それに・・・」
そのときだった、ベットに入っていた零が突然現れて、私に縋りついた。
「あーちゃん、あ・かちゃん・・・」
そう言ってニッコリ微笑んで私の顔を見上げた。私は夾のことだと思ってリビングに持ってきてあったベビーベットを振り返った。すると零は首を振った。
「あかちゃん、いつくるの?」
涼が零を抱き上げた。
「ここにもひとり、待ってる人がいるみたいだからね。産みたくないなんて言わないで、いいから。」
私に表情を見せないで子供部屋に消えた。
涼は優しすぎるよ。ごめん、もう、絶対裏切らないから・・・。
翌年5月、『陸』は産まれた。裕二に良く似た男の子だった。
・・・こんなに自分の子供って可愛いって思うのだろうか。
「本当に、俺の子供・・・なんだよな。」
あきらの前で愚問をした。
どう見たって自分の遺伝子情報を受け継いでいるのは明かだった。
「ありがとう・・・ごめん、嫌な思いをさせて。無理矢理こんなことして。」
あきらが笑顔を見せてくれた。
「裕ちゃん、私が裕ちゃんの赤ちゃんを産むのは運命だったんだよ。他の誰でもない私を選んでくれて・・・ありがとう。陸は良い子だよ、裕ちゃんに良く似た、いい子だから・・・。」
あきらの退院日に連れて来た。
生まれる前、俺が両親とあきらの両親を説得した。
それでも親同士の間では、かなり揉めたらしい。
なにを引き換えにしても陸はこの手で育てたい。
母に、迷惑を掛けるのは分かっている。
でも、母だって陸の顔を見たら黙っていられないと思う、それくらいこの子は俺を魅き付ける・・・完全に親ばかだ。
「あまり長くあきらの手元に置いたら、涼に悪い。」
なんて言ったけど、涼に取られたくなかっただけ。悪いけど涼の子供達より陸の方が全然可愛いから。
22歳で未婚の父になっちゃったけど、平気だよ、陸これからは二人で生きていこうね。
野原裕二の恋はこの瞬間に昇天したと、信じている。
「裕二さん、幸せそうだったね。」
病院からの帰り道、車を運転しながら涼が言う。
「うん。」
私は寂しかった、陸がいなかったから。でもそれだけは言えない。
「あきら、あのさ・・・」
涼が私の肩を抱きしめた。
「お帰り・・・やっと、僕の元に帰ってきてくれたね。僕の・・・」
「涼・・・長い間、ごめんね。」
「長くなんか、ないよ、裕二さんに比べたら・・・本当の事いうと裕二さん一人で子供を抱えて大変なんじゃないかって思っていたんだけど、大変だっていいんだろうなぁ。僕だってあきらがいない
1週間、大変だったけど・・・楽しかった。零も実紅もちょっと良い子になったと思うよ。・・・でも、零ががっかりするだろうな。会いたがっていたから。」
そう言って
「1年くらい遅れてもわかんないかな。」
と、つぶやいていた。
ゴメン、リョウ、ワタシ・・・ユウチャンヲ・・・アイシテイル。
心の中で私が言っていた科白だった。 |
| 第5章・・・うつろひ |
最近、思うことがある。零が小学校2年生、実紅が1年生、夾は6歳、皆私の手元で育って大きくなって。
『陸』がいない。私の陸がいない。
時々、母に電話して『陸』の様子を聞いてみる。でも母は「忘れろ。」と言って、あまり教えてくれない。
いてもたっても居られなくなって、今日の誕生日、私は遠くからでも良いから一目みたいと思って出掛けた。
家の前で誰かを待つように遠くを見つめている幼子。
やがて諦めたように私のいる方向へ走ってきた、私の横を走り抜けて行った。
多分この先に有る公園に行ったのだろう、私も子供の頃、裕二に連れて行ってもらった。
「あきらちゃん?何してるの?」
振りかえると零がいた。
彼は私を母とは呼んでくれない。ずっと名前で呼ぶのだ。
「ずっと、おじいちゃんとおばあちゃんの家に行こうって言っても生返事だったのに。」
零は小学校に入ってからよく一人で私の実家に遊びに来ていた。
「あきらちゃん、陸だよ、ほら、ずっと会いたがっていただろう。」
後ろに隠れるように陸がいた。
零は不思議な子供だった。私がいつも思っていることを見抜いてしまう。
「陸、『ママ』だよ。」
3歳だったのだ、覚えているはずが無いのに、どうして零は知っているのだろう。
「おばちゃん、ママなの?・・・ホントだ、パパの写真に似てる。」
零のうしろから出てきた、陸。
「僕が嘘言うわけ無いだろ?陸のママだよ。」
そう言って背中を押した。
「僕、おばあちゃんにお小遣い貰ってこよう。」
零は小走りに家の中に消えた。
「陸・・・大きくなったのね。」
身を屈めて抱きしめた。
「お誕生日おめでとう。ちゃんとパパやおじいちゃん、おばあちゃんの言うこと聞いて良い子にしていた?」
小さな手が私の背中を抱いた。
「ママ・・・」
消え入るような声で私を呼んだ。離したくない、私の、陸。
ふっと、陸の身体が宙に浮いた。
「なに、してるんだ?」
裕二が陸を抱え上げていた。
「その年頃の女の人を見ると皆ママって呼ぶんだ、気にするな。」
「でも・・・」
「涼と別れて、他の子供達捨てて、陸の母親になってくれるって、そう言うのか?無理だろう。残酷なことはしないでやってくれ、期待、させないで・・・。」
心なしか裕二の背中が震えていた。
「じゃあ、どうして私に陸を産ませたの?陸は私の子供だもの、抱きしめてあげたい。」
私は陸の手を離せないでいた。
「パパいつも『陸のママは遠くにいる』って言ってたじゃない。遠くから僕に会いに来てくれたのに、どうしていじめるの?また遠くに行っちゃったら会えないのに・・・。」
大きな瞳から涙を溢れさせて泣く陸がどうしようもなく愛しかった。どうして5年も放っておけたのだろう。
「陸、また来るから。」
私は二人に背を向けた。そして、零を連れて、家に帰った。陸の側に居る為に。
両親も、涼も一緒になって、考えてくれた。私のやろうとしていることが果たして正しいのか。裕二が陸に母親を迎える気が無いのなら、自分に権利があると思う。
そうして、私達は私の実家に新居を構えた。
「君は裕二さんを愛しているんだよ。」
ベットの中で涼に言われた。
「僕だけを見てろって言ったのに・・・。仕方ないか、彼は君の心の中に種を蒔いていったんだ。子供を産みたいって言われたとき、気づいたよ。あぁ、芽が出たんだなぁって。そして今花開いた。」
「そんなこと・・・」
「大丈夫だよ、僕の花のほうが大きいから。」
優しく、そっと笑う。どうしてあなたはそんなに優しいの?だから私、こんなにわがままになってしまう。
「側に居たって、僕のこと愛してるって思わせてやるから。息も出来ないくらい、愛してあげる。僕についてきて良かったって思う様、いい男になってやるから。」
これは私に対する宣戦布告なのね。
「涼、私・・・涼のこと愛してるよ、本当だよ。隣にいて欲しいのは涼だけだから。信じていてそれだけは。」
10年前、私は裕二の側に居られなくてこの家を後にした。そして今、陸のために自分の意思で戻ってきた。
陸は零に良くなついていて、私といるより、零といるほうが楽しそうだった。
でも、ここまで来ても陸は隣の子供。それでも良い、近くに居られるだけで。
私には零も実紅も夾もいるのだから。
ただ、何かあったら飛んで行って抱きしめてあげたい。
それが私のただひとつの陸への、そして裕二への愛だから。
運動会では転ぶのではないかと思うような足取りで走っていた。
遠足のお菓子を買いに行くといって零を連れ出していた。
こっそりのぞいた授業参観で、振り向いた陸と目が合って・・・でも陸は微笑んでくれた。
私のことを『ママ』と呼んでくれた。実紅や夾と同じ口調で『ママ』と呼んでくれる。
手の届かないものとはどうしてこんなに欲しくなるのだろう。
出来ることなら陸と一緒に暮らしたい。
3人の子供たちと一緒に私の手で育てたい、でも裕二が手放すわけ無いのは分かっていたから、言えなかった。
だいたい、涼になんと言って引き取るつもりなんだろう、私は。
こんな風に私は決して『不幸』ではない、むしろ『幸せすぎるくらい』満たされた気持ちで子供達の成長を見守っていた。
裕二は押しも押されもしない、第一線で活躍する俳優になっていた。相変わらず一人で居たけれど。
涼は去年バンドを離れて、フリーになった。
仕事用にマンションを買って、時々そこに詰めて曲作りとかしているらしい。・・・仕事のことはよく分らないので。
1時間前、涼から電話が入った。
「今、帰るから。」
そう言って。
なのにどうして私はここに居るのだろう・・・。
「あきらちゃん・・・。」
中学1年になった零が私を支えるように隣に座っている。
「大丈夫、涼ちゃんはこんなことで死んだりしない、あきらちゃんを置いて行ったりしないから。」
涼から電話を受けて10分ほどしたときだった。警察から電話が入った。対向車線を走っていたトラックが突然バランスを崩して、飛びこんできた。
幸いにも涼の車の2台前の車に突っ込んだのだが、ブレーキが間に合わず、玉突き衝突を起こした。その真ん中になってしまったのだ。
「涼が死んだら私も行っていい?」
「あきらちゃんがそんな事言ってどうするの。死なない、涼ちゃんは死なないから。」
そういう零の手だって、冷たくなっている。
こんなときになって思う、本当に私が必要としていたのはあなただって。
子供達じゃない、私は涼が居てくれればそれで良かった。
そんな事に気付かずに、陸のことに拘って、涼を傷つけた。ごめんなさい。
私と零は病院の待合室に3時間座って、待っていた。
「毎日来てくれなくていいんだよ。」
申し訳なさそうに涼が微笑む。
「何か、心苦しくて。」
――事故から1ヶ月、怪我は回復に向かっている。なのに、所々記憶がない。特に私とのことは覚えていない。
「まだ言っているの?戸籍も住民票も写真も見せたでしょ。零も実紅も夾もお見舞いに来て納得したんじゃなかったの?あとは何を見せたらいいの?」
「でも、君は裕二さんの婚約者で、子供だって居るじゃないか。」
こんなときに陸の存在がネックになるとは思わなかった。初めて後悔した。
「どうしてそんな事は覚えていて、肝心なことは覚えていないの?」
「ごめん。」
また、涼は謝る。
「大丈夫よ、退院したらきっと、全部思い出せるから。」
今私に出来ることは、不安を無くしてあげる事だけ。
なのにあなたの前にいるとどうしても胸が切なくなる。
「昨日、君が帰った後・・・零、が来た。『どうしてあきらちゃんのこと思い出してやらないのか』って、怒られたよ。」
「あの子はいつもそう、私の考えていること、思っていること、みんな分っているみたいなの。」
「僕よりも・・・」
その後の言葉は、私には聞こえなかった。多分、独り言、よね。
こんなときに限って父が52歳にして海外赴任が決まった。そして、父方の祖母が駅で転倒して骨折、母が世話をしに行くことになった。(父が一人息子だったのはこの時初めて知った。)
「君に迷惑を掛けたくない。」
って、どういうことなの?
しばらく一人になりたいなんて・・・。
母が大事にしていた庭の草木を枯らしたら怒られるので、早朝水をやって、雑草を抜きながら、ぼんやり涼のことを想っていた。
私はあなたの側に居たいって、言ったのに。
・・・涼に甘えつづけていた私への戒め・・・なのかな。
涼を愛しているって言って、裕二を愛した。私には二人が大切だったの。
でも、気付いたよ、ごめんね、涼。
あなたのいない家にいて初めて、あなたの優しさ、あなたの大きさが分かったの。
涼が私の全てを抱えていてくれたんだね。
涼がいないと私、だめだよ、支えてくれないと何も出来ない。
母の様子が変だと気付いたのは、父が退院しても家に戻らず、マンションに引きこもってしまってすぐだった。
僕はちゃんと言ったんだ、父に、
「あきらちゃんと、実紅と、夾を切り捨てないでくれ。」
って。
僕は、いい。僕なんか、忘れたって良いよ、でも、母を忘れるなんて許せない。
僕を見て、母は父の名を呼んだ。似ているからかなって、思ったけど、裕二さんを見ても父の名を呼んだ。
「あきらちゃん、涼ちゃんを迎えに行こう、このままじゃあきらちゃん壊れちゃうよ。涼ちゃんだってあきらちゃんの今のこんな姿を見たら分ってくれるよ、ね。」
母を連れて父のマンションへ行った。そうなんだ、父は、僕に話してくれた。
『あきらを思い出せないんだ、彼女を愛したこと、愛し合ったこと全て。なのに零が僕の子供だってことは覚えているんだよ、変だね。だから、もう少しだけ時間を貰えたら、必ず思い出せると思う。』
そんな、のんびりしていられない。
もう少しの時間がどんどん母を壊して行く・・・。
父は母を見て戸惑った。
母は父を見てにっこり笑った。
でも・・・
「涼、家に帰りましょう。」
そう言って手を取ったのは僕だったのだ。
「ここは私の居るところじゃない。」
僕は決心した。
母が選んだのは僕なのだから、僕が父の代わりになろうと。
・・・本当は選んだのではなく、逃げていただけだったのだが・・・。
「あきらちゃん、セックスしようか。」
何のためらいもなく、母の耳元で囁いた。
父のところから戻ってすぐ、僕は母と関係を持った。そして気付いた、
「僕は母を愛している。」
と。
僕には弟が2人、妹が1人いる。妹にこんな気持ちは抱いていない、一緒に暮らしている弟だってそうだ、可愛いけど、違う。母が何を思っているのか、すごく気になる・・・もう1人気になる人がいるけど・・・
母に僕の気持ちを受け入れてもらったから。偽りでも、良いんだ、僕はあきらちゃんが好きなんだ。僕のモノが母を喜ばせることが出来た、それだけで幸せだった。
「あきらちゃん、髪の毛切ろうね。」
鋏を持ち出し、僕は母の長い髪を切った。
父の好きな母の長い髪、僕は嫌いだ。
父に愛されていると信じている母が、嫌だ。
あの人はもう、母の元には戻ってなど、こない。
僕と、母の時間を奪わないで。
母は、ほんの少しだけ、自分を壊すのを止めたから。
日曜日の午後、母の寝室にあるベランダから、ぼんやり外を眺めている母の後ろに立ち、鋏を使う。
「玄関のドアが開いたみたいだよ、誰か、帰ってきたのかな?」
返事のないのは分っているけど、声を掛ける。階段を人が上がってくる気配・・・でも、これは、この足音は・・・実紅でも夾でも祖父母でもない・・・。
「なにをしたんだ、零。」
ドアを開けて父が立っていた。
「ここに、あなたの居場所はないよ、もう。」
次の瞬間僕の頬が悲鳴を上げていた。痛みより悲しみが僕を襲った。
「あきらは、僕の女だ、手を出すな。」
父の口から吐き出された、生臭い言葉。母の身体を父が奪い取る。
「記憶、無くしていたくせに、いくら頼んでも戻ってこなかったくせに。」
今更手を握り返そうなんて卑怯だよ。
「一生賭けて償うから、あきらにも、零にも。」
「僕、あきらちゃんとセックスしちゃったよ。笑っていられるの?近親相姦、わかる?僕もあきらちゃんと一緒、狂っているんだ。」
僕は二人に背を向けた。
「分ってる。守ってくれていたんだろう?感謝している、零には。」
母をベットに腰掛けさせて、父は僕を抱き寄せた。
「ごめん、まだ、子供なのに、お前に全部抱えさせて、甘えて、困らせて・・・寂しい思いをさせて。」
僕は父の腕の中で泣きじゃくっていた。――寂しくなんてなかった、本当に愛していた。――
父と入れ替わりに僕は家を出た。母への想いを封じるために。同時にもうひとつの想いも、断ち切るために。
母を絶望の淵に追いやったのは父だったかもしれない。でも、本当に壊してしまったのは僕だったのだろう。
なぜなら母は、初めて僕が抱いた夜、ちゃんと抵抗したのだから。抗う母を無理やり犯して、泣かせて、子供を産ませた。
父は否定した、この子は自分の子だと断言したけど、分るよ。僕の子だ。
父に帰ってきて欲しかった、裕二さんに頼ろうかとも思った。
でも僕は僕のやり方で1人の女を愛したのだ、後悔などしていない。
『聖』の誕生日は僕が母を失った日。父が母を取り戻した日。
母は父を見て笑った・・・そのまま時を止めた。 |
| 最終章・・・たゆら |
どれくらいの時を過ごしたのだろう。
僕の腕の中であきらが微笑む。
でも、心はここには無い。
失って気付いた、『僕はこの人を愛した』という事実。
・・・記憶なんてどうだっていい、僕はあきらを幸せにしなくちゃいけなかった、したかった。
なのに全てを放棄して、零に押しつけるような事をしてしまった。
その報いだね、『聖』は神様が僕に与えた最大の罰なんだね。
聖が生まれる前までは、僕の声を聞いてくれていたはずだった。
しかし、あの日から心も耳も目も・・・何もかも開かれなくなった。
あの子が僕の子じゃなかったから?
だから帰ってこないの?
だったらもういいから、僕が全部抱えてあげるから、君は何も考えなくていい、帰っておいで・・・。
零は誰からも僕の子だね、って言われる。それくらいよく似ている。
聖はその零に似ているなんて皮肉だ。
本当は裕二さんの子供だったらって願っていた。
僕がほんの一瞬でも手を離したから、裕二さんが抱きとめていてくれたのだとしたら、それだったらきっと、僕は2度とここへ足を踏み入れようとはしなかっただろう。
でも、抱きとめたのは零だった。
愛したのは零だった。
「パパ、ママは私が見ていてあげるから大丈夫。お仕事してよ。・・・パパを待っている人達が沢山いるでしょう?」
実紅が僕の肩に手を置いて優しい声で言う。
「ん、でも、一緒にいたいんだ。一杯泣かせちゃったから。」
実紅・・・秋に産まれた女の子。千両の真っ赤な実が僕の目に映って、この子の頬が真っ赤だったので実紅と名づけた。とっても静かな子供だった。もうこんなに大きくなったんだね。
「聖ちゃんはおばあちゃんが見ていてくれてる。でも、おばあちゃんも来月にはおじいちゃんのところに行っちゃうんでしょ、どうしよう。」
「ばかだなぁ、だからパパがいるんだろう?」
「どうしてお兄ちゃんは1人暮ししているの?」
「疲れちゃったんだ、パパが1年近くママのこと頼んじゃったからね。」
「そっか・・・。ママはパパがいてくれればいいもんね。」
あきらに向かって実紅が微笑んだ。
ほんの僅かだったが、あきらの口辺が、目元が動いたように思えた。
「実紅、ママが『そうだよ』って言ってる。」
「・・・パパ、それはのろけって言うんだよ。ねぇ、ママ。・・・パパ、少しママと二人でお話していてもいい?」
黙ってうなずき僕はリビングを出た。
「涼、仕事辞めるのか?」
「裕二さんと違うからね、僕は。自宅で出来る仕事があるんだ。」
久しぶりにオフィスに顔を出したら、裕二に会った。隣に居るのにめったに会わない。
飲みに行こうと誘われて、彼の行きつけの居酒屋に来ている。
「裕二さんと居酒屋って似合わないなぁ。」
隠れ屋のような趣の店内を見渡した。
「そうか?・・・ところで、単刀直入に聞くけど、あきら・・・奥さんの具合はどうなんだ?」
「・・・あきらで、いいよ。・・・特に変化は無いかなぁ。陸君にも嫌じゃなかったら会ってやってって言っといて。」
「ああ。」
随分長い間、二人とも、何も話さなかった。
沈黙を破ったのは裕二だった。
「涼があきらを捨てたとき、俺、躊躇ったんだ。今だったらあきらを自分のものに出来るかもって、そう思ったのに・・・足が竦んだ。また、拒まれることを恐れたんだ。・・・だから黙っていた。正解だったな。」
僕の猪口に銚子を傾けながら裕二さんは付け加えた。
「結局、保身に走ったんだ、俺は。」
「僕だって、自分が可愛いよ、だから、あきらを一人にしてしまった。」
「誰にだって、失敗はあるさ、そうじゃなかったら悩まなくたっていいだろ?」
裕二さんは以前の尖がった雰囲気が削げ落ちて、丸くなったようだ。
「今の俺は陸しか見えない。すっかり親馬鹿。」
そう言って、笑った。
人間、本当に守れるものは一人なのだろうか。
「夾!」
そっと階段を上がっていた足を止めた。
「今、何時だと思っているんだ、こんな時間まで何していたんだ。」
時計は十二時を指していた。
「・・・いいじゃないか。パパはどうせ僕に興味なんて無いんだろう?」
・・・そうなのだ、僕は夾に逆恨みの感情をもろにぶつけていたらしい。夾が産まれなければあきらは裕二と関係を結ぶことが無かったと思っていたらしい、「らしい」のは覚えていないから。義母に聞か
されたことだった。だから今は気をつけて接するようにしている。・・・覚えていないのだから、平気だとは思うけど。
僕は黙って夾の頬を張り飛ばす。もちろん、手加減している。
「ぶたなくたっていいじゃないか。・・・兄ちゃんのとこに居たんだ。ここは息苦しいから。」
「だったら電話すればいいだろ、それに遅くなるんだったら・・・」
泊まってくればいい、と言いかけて言葉を飲みこんだ。
「心配、するだろう、迎えに行くから、連絡しろ。」
言ってから、背をむけた。
『息苦しい』・・・ショックだった。
僕は夾になにもあげられないのだろうか・・・。夾竹桃の花が庭に満開に咲いていた夏の朝、出産に立ち会った。「立ち会った」とは言っても、零のときは地方にいて、実紅のときはスタジオに篭ってて、
ちゃんと病院に来られたのは夾が初めてだった。
なぜだろう、夾が生れ落ちた朝のことは鮮明に覚えているのだ・・・。
産まれてすぐに夾の顔を見た。
小さな手が何かを求めるように宙をさまよっていた。
その手を今、捉まえたいと思うのは僕のわがままだろうか。
「涼ちゃん、お願いがあるんだ。」
零が僕に頼み事するなんて、僕があきらの元を去った時以来だ。
「なに?」
「プロになりたいんだ、でもどうしたらいいのかわからなくて。」
「プロ?・・・って、」
「うん、僕達のバンドをメジャーデビューさせたいと思って。」
「そっか。」
『デビュー』・・・懐かしい言葉だった。そのときふと思い出したことがあった。
「・・・そうだ、デビューが決まった時僕はあきらと一緒に、居た。」
「涼ちゃん?何か思い出したの?」
「うん、ちょっとね。いいよ、手を貸してあげる。でも貸すだけだから、後は自分達でやれよ。」
「ありがとう・・・。それと・・・聖はどうしている?」
お互いに視線を落としてしまう。
これじゃ聖が可哀想なのは分かっている、聖は僕の・・・子供だって、思いたいけど・・・だめだよ、僕はあきらとずっとしていないから。
「うん、隣の陸君がよく遊んでくれるんだ、助かっている。実紅は学校が忙しいし、夾は受験だってうるさいし・・・陸君に頼りっきりで。」
「・・・涼ちゃん、陸のこと、どう思ってる?」
突然零は痛い所を突いて来るんだ。
この子はいつもそうだ、あきらが昔言っていたな。
「どうって・・・いい子だよ・・・あきらの産んだ子だから。」
「じゃあ、聖も愛して。あきらちゃんの産んだ子だから、愛してあげて。」
必死の瞳で僕を見つめる。
「・・・愛してるよ、精一杯、愛してる、つもりだけど。」
「憎むなら、僕にして。聖は関係無いから。」
そうか、零はそれが言いたくて来たんだね。零は確かに聖の父親なんだ。
「誰も憎んでなんかいないよ、零も聖もあきらも、愛してるから。」
零に僕の気持ちは届いているのだろうか。
どこまでいっても闇の中のように暗くて、僕は手探りで君を探していた。
何回朝を迎えただろうか、何回夜を過ごしただろうか、もう数え切れないくらいの日々を返事の無いあきらと過ごした。
零が抱えようとしていたことを僕に出来ないわけ無いじゃないか、なのにもう切ない。
零が聖を連れて行った。やっぱり僕では信じられなかったのだろうか。
実紅が裕二と結婚すると言い出した。しかも既に妊娠していると言うのだ。たった一人の娘が父親より年上で、母親の元婚約者で、しかも母親に義弟を産ませた男の元に嫁ぐと言う。
「本当にいいのか?」
「うん、私裕二さんのこと好きだから。」
その瞳が揺れていたのを気付かなかったわけではないけど、この子は言い出したら聞かないから、裕二に預けることにした。ごめん、僕は父親失格なのかもしれない。
あきら、ねぇ、ずっとそこにいるの?ずっと帰ってこないの?
眠れない夜、僕はあきらの身体をそっと抱きしめる。
もう一度ゼロからはじめよう、たった二人で、二人っきりで。
「涼ちゃん。」
ゆめうつつの頭で何か考えていた。
――あきら?――
そっと、目を、開けた。
にっこり微笑むあきらが、いた。
「なんか、一杯夢を見たの。」
視界がぼやけてきた。
「ん・・・」
「どうしたの?どこか痛いの?まだ具合良くないのね?」
君は一体、何年眠っていたのかな・・・あれから、7年の月日が流れたんだよ。
もう、零も実紅も、聖もこの家からは居なくなった。何故かあんなに僕に反発していた夾がここにいて、ずっと僕の手助けをしてくれている。
あきらを治すのは僕だって言って、今、医大に通っているなんて聞いたらびっくりするね。
夾、がっかりするかな、いや、きっと喜んでくれるね。
やっと、ママが帰って来たって。
途中で気付いたんだ、夾は零以上にマザ・コンだったんだ。
あぁ、N.Yのお義父さんお義母さんに電話して、それから零にも。
隣の家にいる、実紅にも教えてやらなきゃ。
「あきらが帰ってきたよ」
って。
僕達の前奏曲がゆっくりと奏でられていた、時間だった。
<前奏・・・『狂想曲』より>END |
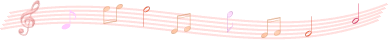 |
 |