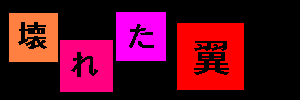 |
| − 前編− |
女子高生でもあるまいし、夜道が怖いわけ無いじゃないか。
しかし現代の常識は違っていた。
僕はその日から強姦魔の恐怖に怯えることになる。
部活が終ってファミレスで食事を済ませたら随分遅くなってしまって、僕はてくてくと誰もいない夜道を歩いていた。
別れ道に差し掛かった。一方に行くと山道になり街灯もないので夜通る者はいない。途中に墓地があるのも原因の一つだ。
突然、音も無くそいつはやって来た。
背後から羽交い締めにされた。その後は簡単だった。自分が着ていたもので自分の身体を拘束されるなんて馬鹿みたいだ。身動き一つとれなかった。墓地までズル
ズルと引きずられるように連れて行かれた、声を出すことも出来なかった。
「うーうー」
唸ることだけが意思表示だった。
一時間ほどたっただろうか?僕は全裸のまま、道端で呆けていた。
…強姦…自分の身に降りかかるなんて。
『誰かに言ったら、殺す』
と脅されてしまった。
『また、気持ち良くしてやるから』
そう言って、立ち去った。気持ち良くなんかなかった、ただ痛くて…。
男が男を強姦するのか?そんなのって、変態じゃないのか?僕を狙ったのか?それともたまたま通りかかったのが僕だったのか?…また…またがあるのか?ってこと
は僕って分かっているってことで…。
やっと思考回路が繋がった頭を持ち上げて自分を拘束していた物を必死で剥がす。それを身に着けるなんて情けなかった。だけどそれ以外着る物も無く、仕方なくって
感じだった…と今では思うけどその時は必死だったんだ。
人に言ったら殺す…その言葉が脳裏を離れず、僕はただ1人で恐怖に耐えていた。
その日は意外と早かった。
あの日から怖くて夜道が歩けなくなっていて、部活もずっと休んでいた。
しかし、そうそう休んでいては折角獲得したレギュラーを降ろされるので終ったら寄り道せず、とっとと帰れば大丈夫だろうとたかを括っていた。
「安斉、お前どうしたんだよ、最近付き合い悪いぞっ。」
「ごめん、どうも体調が悪くってさ、良くなったら付き合うからさ。」
などと言いながら既に着替えを済ませてドアを出ていた。
暗くなりかけた道を前だけを見て小走りで必死に歩く。
襲われた場所はもうすぐだ、今日も心臓が跳ねあがる。ドキン、ドキン…怖くて走る事も出来ない…。
コチコチに固まったまま、僕は恐怖の場所を通り過ぎた。
何となくその場所を通り過ぎたことで僕はホッとしていた。
ほんの少しだけ足取りが軽くなり、速度も遅くなった瞬間、ヤツは現れた。
「残念だったね、急いで墓地の前を通り過ぎたみたいだけど約束はどこでも守れるんだよ。」
そこは時々1週間程度、東京から金持ちがやって来てドンチャン騒ぎにだけ使う、贅沢な別荘。だからここで少しばかり大きな声を出しても誰も相手にしない。相手に
すると執拗に嫌がらせを受けるからだ。
その贅沢な金持ちは一昨日、この地を後にした。また暫くやって来ないはずだ。
折角静まった心臓が、さっきよりも大きく鳴る。
どうやって屋敷の中に連れ込まれたのか分らないほど、僕はショックを受けていた。屋敷の中は真っ暗だった。
「やっと捕まえた。」
…また、犯される…
外傷がやっと癒えたばかりなのにまた裂かれてしまう。それより心の傷がまた深くなる。
男はそっと、僕の唇に唇を重ねた。ただ重ねただけ。
「怖がらないで。」
そんなこと言ったって…。
「愛してる。」
なに?それ?
男の指の動きが、暴力から愛撫に変わる。
耳朶を軽く噛まれ、背筋がゾクッとした。これはきっと恐怖。
僕の身体を這う唇と舌は、首筋を伝い鎖骨を辿る。ゾクゾクした。
「うっ」
乳首を探り当てた男は徐に噛んだ、そして吸う、舐める。それを飽く事も無く繰り返す。次第に乳首は快感を覚えぷっくりと起ち上がった。左が済んだら右。
「あぁん…」
気付いた時、僕は喘いでいた。
男は乳首を弄りながら僕のズボンを脱がす、でも僕はそれに気付かないくらい快感に喘いでいた。
…どうして?どうして僕が喘いでいる?…心の奥のほうではそんな言葉が繰り返し繰り返し、呟かれているのに、性的欲望が旺盛な年頃、快感には抗えなかった。
「あぁん、あん、あんっ」
もう、壊れた様に喘いでいる。
…もっと、もっと大きな刺激が欲しい…そんな事を思っていたその時、
ズグッ
と、何かが挿入された。しかしそれはとってもスムーズに、自然に、入ってきた。
ズクッ、ズクッ
抽挿される異物、身体を這う舌。
異物の抽挿は延々と続いた。段々と麻痺する入り口。
僕の唇は無意識のうちに唇を求めていた。
「キス…して…」
身体を這っていた舌が嬉しそうに僕の舌を絡め摂った。僕はそれを貪った。男の唾液が流れ込んでくる、僕の唾液が掬い取られる。男の鼻息が荒くなる。
異物の抽挿はまだ続いていた、何時の間にか数が増えていた。
「あぅっ」
物凄く、気持ち良い場所を異物が擦る。何度も何度も擦る。
「あんっ、あんっ」
欲望が透明な液を出し始めた。すると男は躊躇いも無く口に含み2〜3度しごかれる。
「あっ、あっ、ああああああ」
簡単に頂点に上り詰めた。
ぺロリ、男が舌なめずりする音がした。
「もう十分ほどけたね、この間は無理に捻じ込んで傷つけてしまったね、ごめんね。」
射精した快感で肺がゼイゼイいっている僕の身体に、男の素肌が重なった。本能で感じた、恐怖。身体が強ばる。
「力を抜いて」
優しく、耳元に囁かれた。その声に何故か安心していた。聞き覚えのある、優しい声。
男の唇が三度重なる。僕は躊躇わず舌を絡めた。再び身体が快感を求め始める。
右足だけ抱え上げられた。
ズブリッ
「ひっ」
一瞬、痛みを感じた気がして力が入った。でも痛くなかった。
「あぁっ、やっぱり洋〈ヒロシ〉の中は良い…」
…こいつ、僕の名前を知っているのか…
ぼんやり、そんな事を考えていた。逃げられないことを悟った。なら快感に身を委ねてしまおう。
男はそっと動き始めた。
ズリュ、ズリュ…
「あんっ、あんっ」
動きに合わせて喘いでいるのは自分。
「あっあっあっあっ…もっともっと…イイッ」
僕はおかまだったんだ…突っ込まれてイイなんて口走っている。だけど本当に気持ち良いんだ。
1回イって力なく項垂れていた物が飛び起きる様に起ち上がった。
ビクン、ビクンッ
2度目は触れられる事も無く、イった。
男もイったらしく、僕の上でゼイゼイと息をしていたが、すぐに起き上がると抜かずにゴソゴソと何かを探していた。
パッ
フラッシュ…また恐喝か…。
「洋…最高だったよ、また愛し合おうね。あっ、そうそう、学校を休むととんでもない事になるからね。」
そう言い残して男は去って行った。
…何だよ、とんでもない事って…僕の中にはモヤモヤした思いと男の精液が残された。
翌日、学校の机の中にピンクの封筒が入っていた。クラスメート達は「ラブレターだ」と大騒ぎしていたけど、いや、確かにラブレターだったけれどもそれは男からの
ものだった。封筒と揃いの便箋にはだらだらと愛の文句が書かれていた。そして最後の便箋には不鮮明な写真がプリントしてある。僕にはわかる。夕べイカされた後
、繋がったままの写真だ。それをわざと画像を落してあるのだ。
「なんだよ、呼び出されたのか?」
「まぁ、な…」
「このぉ、女殺し、ニクイね。」
僕は力なく笑うしかなかった。
「絶対、着いて来るなよ。」
僕の喘ぎ声を聞きたくなかったらな…、もう自棄だ。
僕は呼び出された場所に向かった。もしかしたら本当に僕はおかまかもしれない。だって犯される…と決めつけていたのだから。
呼び出されたのは化学実験室、だけど途中で腕を引っ張られ連れ込まれたのは社会科準備室。古い紙の匂いがたちこめる、なんとなくじめっとした陰気くさい部屋
。当然真っ暗闇だ。
「ちゃんと来てくれたんだね。」
そう言って男は僕を抱き締める。
「来なきゃ、あの写真ばら撒くんだろ?」
「洋の行動次第だね。」
カチャ
鍵の掛かる音、下半身が疼いた。
「まだ、僕が分からないの?愛情が足りないよ。あんなに感じてくれたのに。」
唇が重なる。
クチュ、クチュ、クチュ…深く、深く口づける。唾液の交換。糸を引くほどのキス。
「安斉 洋、17歳。成績は150人中大体25番位を行ったり来たり。部活はテニス。彼女はいない。両親と兄貴が2人の三男坊。そうそう、チロという名の猫を飼ってい
たね。性格は至って明るく、クラスでも目立つ方、だけど最近元気が無い…どうして?まさか僕のせいじゃないよね?だって洋は僕とのセックス、喜んでくれていた。」
男は言いながらシャツの中に手を入れて僕の乳首を弄る。
「あっ、アンッ」
「しっ、今は大きな声を出しちゃ駄目だよ。外に漏れる。」
「だ、だけど…うふんっ」
「可愛い声だね。もっと苛めたくなる。」
シャツの前をはだかれて直接口に含まれた。
「んんっ」
男の髪を掴み快感に耐える。
「これからもっと気持ち良くなるけど、声出さないでね。」
「ふあっ」
ズボンのファスナーを下ろされ、そこから取り出されたペニスを口に含まれた。
ジュプッ、ジュプッ…イヤらしい音…。
ドクッ、ドクッ…あっという間に上り詰めた。
「洋…僕のも、して?」
快感の余韻に浸るまもなく、強引に跪かされ口に押しこまれる。
イヤダ、イヤダ、イヤダ…そう思いつつ、唇を窄めてすするように舐める。
「あぁ、イイ、いいよ、洋…」
どうして僕はこの男に対して抵抗しないのか?それはこの男が僕より体格が良く、腕力があるから。たぶん平手打ちをくらったら顔が吹っ飛ぶんではないかと言うほ
どの大きな手…。違う…本当は快楽の誘惑に勝てないからだ。その証拠にこの手に包まれただけで温かくて気持ち良くてイってしまう。
「そうそう、大事な事忘れていた。洋は…童貞だよね。」
ピタッ。動きを止める。
「ごめん、気にしていた?でもいいんだよ。洋は僕のもの…この先もずっと…ほら、ちゃんと動かして。写真、掲示板に貼るよ。」
慌てて僕は動く。
「もっと…舌、使って…違…う・・・」
遂に男は僕の頭を両手で挟んで腰を動かした。先端が喉に当たって吐きそうになる。
「出るよ」
言うと同時に男は精液を放った。
「全部飲んで。僕も飲んだでしょ?」
飲むって…これを?
両手で口を押さえて我慢して飲みこむ。不味い…。
「洋は溜め込んじゃうからね、ちゃんと処理しなきゃね。」
どうして、そんなことまで知っているんだよっ。
「いい加減にしろよ…誰だよ、お前。」
バンッ
僕の身体はふっ飛んだ。だから平手打ちを食らったんだな…って気付いた。
「僕に対してそういう口の聞き方は許さない。洋が分るまで教えない。」
男は準備室を後にした。しかしこの時一瞬だけど後姿を見た。確かに見覚えのある後姿…だけどあの人のわけ、絶対にない…でも声を聞いた時、うっすらと思って
はいた。そしてあの大きな手、広い胸板、ガッチリとした肩幅…。
信じられないよ…信じたくないよ…あの人が強姦魔だなんて…。
僕の頬はぷっくりと腫れていた。
「安斉すっげー顔だな、もしかして振ったのかよ。駄目だなぁ女を怒らしちゃ。もっと上手く断らなきゃ…っておいっ、何処行くんだよ、安斉っ、サボるのか?おーい。」
クラスメートの声なんか無視だ。もう校内にいられない。ここにいたら又犯される。慌ててカバンを握り締めて学校から逃げ出そうとした。
駆け足で昇降口に向かう。
「駄目ですよ、安斉君。僕の授業をサボろうなんて。」
「離せっ。」
「単位を落しても良いのですか?」
「どうせ…ずっと恐喝されるんだろ?だったら学校辞めてお前のいない所に行く。」
「今の世の中、インターネットとかもあるんです。簡単に誰でもアクセスできます。」
「何が楽しいんだ、僕を強姦して恐喝して…金なんか無いぜ、まだ高校生だからな。」
「言ったでしょう?愛しているんです。」
柔道でオリンピック代表候補になるほどの選手だった英語教師、蜜佐波〈ミツザワ〉が強姦魔の正体。
「愛していれば強姦していいのかよ?」
「強姦?どうして?僕は合意の上だと思っていますけど。」
「どこが合意なんだよ、殺すって言ったり、無理矢理突っ込んだり…」
「腰を振っていました、メスの様に。」
「それは…」
「感じていました、もの凄く。」
「大体、愛してるって僕もお前も男だろ?」
「いけないのですか?」
「気持ち悪いっ。」
腕を掴まれ、公の場でキスを貪られた。幸い始業ベルが鳴った後なので誰もいない。
「んふっ」
「ほら、感じている。これでも気持ち悪い?」
「だけど…」
「世間体とか道徳に縛られすぎているからです。そんなの昔の人が決めた事。人が人を愛して、何の罪があるのですか?
はい、教室に戻りましょう。…今日は僕の家でたっぷり可愛がってあげます。」
僕は蜜佐波に背を押され、俯きながら教室に戻らされた。
もう…逃げられない…僕は完全におかまになってしまった。
「はっ、あぁっ」
「可愛い、僕の洋…もっと感じて…」
薄給の教師にしては豪華なマンションだった。玄関から寝室まで辿り付くのに3つはドアを通りすぎた。
寝室のベッドはキングサイズ。
初めて明るい部屋の中で強姦魔…蜜佐波に裸を晒し、犯される。
蜜佐波は僕が意識を失うまで犯し、気が付くまでまた犯す。
朦朧とした意識の下、僕は喘いでいる。もう完全に壊れてしまった僕の性感。
「あっ、あっ」
いくら掻き回されても舐めまわされても僕の半身はピクリともしない。だけど身体の内部は今まで以上に感じてしまっている。
ぼんやりと目覚し時計に視線を移した。学校からここに連れ込まれて既に10時間が経過している、午前2時。明日は休日の土曜日…きっと日曜日の夕方まで、い
や月曜日の朝方までずっと犯されるのだろう。
あぁ、気が狂ってしまえたらどんなに楽だろう、そうしたらただ快感に身を委ねて、一緒にセックスを楽しめるだろうに。だけど僕は普通の高校生だから。
ビクッ、ビクッ
僕の中で蜜佐波が13回目の射精をした。26歳の青年はこんなに精力旺盛なのだろうか?そんなことを考えていた。
グチュッ
蜜佐波のペニスが引き抜かれたとたん、ドロリと大量の精液が僕の中から溢れ出す。
「洋、疲れたのかな?だから起たないのかな?少し眠っていいよ。」
あぁ、眠って良いんだ…コクリ頷く。僕の口はもう、喘ぎしか漏らさなかった。
そして深く深く眠りに落ちた。
ピチョン…ピチョン…水の音。眠っている間にバスルームに連れて行かれていた。
うっすらと目を開く。
「目が覚めちゃった?ごめんね。だけど僕が汚してしまったから綺麗にしようと思って。あぁ、でも洋は綺麗だよ。ピンク色の乳首、ピンク色のペニス、ピンク色のアヌス
。どこもかしこもピンク色でドキドキしちゃったよ。そうそう、朝食が済んだら家に帰りなさい。ご両親に心配を掛けてはいけないからね。夕べはちゃんとお母さんに電話
を入れておいたから安心していいよ。ちゃんと真面目に勉強したと伝えるんだよ。」
勉強…なんの勉強だよ。強姦魔に身体を好き放題にされたときの対処法か?
頭がガンガンする。
こいつ、何を考えているんだ?だけど帰れるなら何も言うまい。僕は相変わらず黙ったまま頷いた。
家に帰ると蜜佐波の言う通り誰も疑問を抱かず、反対に勉強熱心だと誉められた。
すぐに部屋に戻ってベッドに潜った。
眠ってしまおう、眠ってしまえば全て忘れられるから…。
だけど神様はそれを許してくれなかった。目を閉じるとほぼ同時に眠りに落ち、卑猥な映像が瞼の裏に映し出される。犯しているのは蜜佐波、犯されているのは自分…
「嫌ぁー、やめてぇー」
自分の声に驚いて目が覚める。
それを何十回も繰り返し…僕は望み通り狂って行った…
|
− 後編− |
「洋?洋まだ寝ているのか?いい加減…」
ドアを開けた僕は次の言葉が出てこなかった。
僕の姿を見留めると毛布を抱えてベッドから飛び降り、部屋の隅で身体を小さく丸めてガタガタ震えているのだ。
ゆっくりと近づいて行き髪に手をかけたとたん、
「嫌、もう嫌だよ、助けてよ。口でしてあげるから、入れないで…」
顔も見ずにそう言われた。
「何の、ことだ?」
「口じゃ、駄目なの?僕頑張ったのに。ちゃんと飲むから。」
口でって…飲むって…なんだろう?
ゆっくり這いながら洋は近づいてきた。そして恐る恐るズボンに手を掛けて引き下ろす。
「おい、何すんだよ、冗談は止めろよ。」
「お願い…」
涙で潤んだ瞳は、しかし焦点が定まっていない。
「お願いったって…」
洋の手は、僕の下着に掛かりするすると剥ぎ取られた。
「いい加減にして…」
すごっ…気持ち良い…何も考えられないほど、良かった。あっという間に僕の息子は元気になってしまった。
洋の肩を食い込むほど握り締める。
「はぁっ…うっ…」
僕は洋の口の中で発射してしまった。
コクリ…音を立てて洋は僕の精子を飲み下した。耳が火照って熱くなる…。僕は慌てて洋を自分から引き剥がし、下着を引き上げた。
「洋…どうしちゃったんだよ?」
洋の瞳はまだ視点が定まらないまま怯えている。
「洋…」
僕は洋の身体を抱き締めた…。
「で?」
太一はぶっきらぼうに返事をした。
「いきなり洋に脱がされて…。」
「上手かったのか?」
真っ赤になって頷く。
僕は両親に悟られない様に洋を連れ出して兄のアパートへ来た。兄は洋の様子を見て、一目でヘンなことに気づいたらしい。
「昨日、帰ってきたときは疲れた様子だったけどちゃんとしていたんだ。それがトイレにも出てこないのでおかしいと思って覗いたら…こうだった。」
そのときだった、洋が突然身体を小さく丸めて叫んだ。
「ねぇ、先生。僕ちゃんと飲んだでしょ?誉めて…だからもう入れないでぇ…」
僕たちは顔を見合わせた。太一は
「んー」
と唸った後洋を全裸にした。
「ヤダよ、セックスはもう嫌だよ…」
そう言いながら洋は四つん這いになって尻を突き出した。
ぺロリ、人差し指を舐めると洋の穴に指し込んだ。
「あぁんっ」
ゴソゴソと中で指を動かしてみているらしい、その度に洋が女の様に喘いでいる。
「多分…そうなんだろうけど一応アレ、とってくれるか?」
太一が僕に向かってそう言った。
「アレって?」
「バイブ」
「…なんでそんなものがあるんだよ。」
顎で僕に指示して目的の物を手にすると太一は唾液でたっぷり濡らした後、ズブリと洋に突き刺したのだ。ゆっくりと引き抜くと名残惜しそうに腰を突き出し、突き入
れると歓喜の声を上げる。
「にいちゃん、止めてくれよ。洋が可哀想だ…」
「そうだな、誰かに強姦されてそのまま関係を強要されたんだな…相手は教師。」
「分ったよ、そんなことはあとでいいから。」
「あぁ。洋今気持ち良くしてやるからな。」
バイブの抽挿を繰り返し、手で洋のそれをしごいた…しかしピクリともしない。
「こいつイカレタみたいだ。」
「洋…」
洋は空ろな瞳のまま腰を振っている、僕はただそれを涙のカーテン越しに見つめるしか出来なかった。
「にいちゃん…」
兄の狭いアパートの一室で洋は大人しく眠っている。兄と僕は壁に背をもたせかけ並んで座っていた。
「あのさ…」
聞きづらいけど聞くしかないだろうな…。
「聞きたいことがあるんだけど…」
兄は多分知っている。
「…なんだ?」
「うん…」
それでも躊躇ってしまう。
「男が、男を強姦って出来るのか?」
「洋はその被害に遭ったんじゃないのか?」
「さっきみたいに…尻に…入れるのか?」
「…口も、そうだろ?」
そうだった、いきなり咥えられて僕は動揺したのだった。
「気持ち、いいのか?」
「平〈タイラ〉は経験、あるのか?」
「男、とか?」
「ばかっ違うよ、セックスだよ。」
「あぁ。まあな。」
経験っていったってほんの数回だ。
「洋は…あったのか?」
「童貞だって…言ってた。」
つい先日、そんな話をしたばっかりだった。だからセックスに期待や憧れを一杯持っていたはずだ。
「そっか…じゃあ実行に移したんだ、これ。」
ポンッ、兄が投げて寄越したのは一通の手紙。
「読んで良いのか?」
「あぁ」
ガサッ、僕は手紙を開いた。
親愛なる太一くんへ
もう何通目のラブレターだか忘れてしまうくらい書いたね。だけどそろそろ限界だ。君の可愛いがっている大事なものを一つ、壊すとしようか。
「なんだ?これ…」
「蜜佐波って教師、覚えていないか?俺が3年でお前が1年の時新卒で採用された東大出の教師。あいつはゲイなんだ。」
蜜佐波って…?
「…ああ、柔道部の顧問か?僕も、口説かれたことがあるよ、てっきり冗談だと思っていた。…あいつか?犯人。」
「たぶん…週に2〜3通はこんな風に手紙が届くんだ。もうずっと…」
「…あいつ、洋を好きなんじゃなくて兄ちゃんが好きで、犯ったのか?」
「分らないけど、俺に執着しているのは確かだ。引越し先なんか誰にも教えなかったのにこうやって手紙が届く。それも引越しした当日からだ。」
兄はガールフレンドに不自由しないほどもてる。僕も途切れることがなく彼女はいる。しかし洋は照れ屋なのでなかなか踏みきれなかったらしい。
兄が左手の親指の爪をガリガリ噛んでいる、何か考えているのだ。
「うわぁー、止めてぇー」
突然、洋が叫んだ。
「洋っ」
僕は洋の側に飛んで行った。
「大丈夫だ、もう大丈夫だから…僕が守ってあげるから、洋は良い子だから、ね?」
子供の頃、喧嘩に負けて帰ってきた洋を、母は意気地なしと罵った。しかし僕は洋がとっても優しい子だって知っている、誰かに力で勝ちたいと思わない子だって
知っている、だから僕が、守っていた。
「たいら…」
くすん、と鼻を鳴らして僕の胸に顔を埋めてくる。
「怖いんだ、僕…助けて…」
「洋?」
洋の瞳が真っ直ぐに僕を見つめている、ちゃんと僕だと分って話している。正気に戻ったのだろうか?
「先生が、僕のこと…」
僕は兄の顔を見た、兄も僕の顔を見た。
「洋、どの先生だ?」
「写真…撮られてて…誰かに言ったらばら撒く…って…」
うぅ・・・と、嗚咽が漏れる。
「誰だ?そいつは。」
兄が低く訊ねた。
「…蜜佐波先生…英語の…」
「やっぱりそうか…」
兄はすっ…と立ちあがり「出かけてくる」と言い残し、外へと出ていった。
「僕ね、やきそばはたいらくんの作ってくれるのが1番好きなんだ。」
お腹が空いた…と騒ぐので冷蔵庫を適当にあさって作ってあげたんだけど、洋はとても嬉しそうに食べていた。
「そっか…」
…洋は確かに正気に戻ったように思える。だけど…ちょっと違うんだ。
洋が僕のことを『たいらくん』と呼んでいたのは小学校6年まで。口調もちょっとおかしい。
「にいちゃん、何処行ったのかな?」
「うん…」
僕の空返事に洋は黙り込んでしまった。
目覚し時計がうるさく時を刻む。外では車が走り去る音がする。
「たいらくん…僕…ヘンなんだ。お尻にちんちんが入っちゃうんだ…で、すっごく気持ち良くって泣いちゃうんだ…だけどそのちんちんは嫌いなんだ…だから又泣く
んだ…ずっとそんな夢を見ていた。」
危なく耳を塞ぐところだった。そうしたら最後の言葉を聞き逃していただろう。
「…夢?…」
「うん、嫌で嫌で目が覚めるの、ヘンなおじさん、僕嫌い。」
さっきははっきりと『蜜佐波先生』と答えたのに今度は何度聞いても『ヘンなおじさん』としか言わない。
「だって知らないんだもん、あんなおじさん。身体も手も足もでっかいんだけど、ちんちんはちっこいんだ。」
ふふふ…と可愛らしく笑う。
「だから寝る前に神様にお願いするの。『たいらくんがいいです』って。」
…なんで、僕なんだよ…
「僕、おかまになっちゃったんだ。だからたいらくんとえっちがしたい。ね、して?」
言うが早いか、洋は僕の下半身を剥き出しにしてペロペロと舐め始めた。
「洋、いい加減にしろっ。」
僕は理性が保てる間に洋を叱り付けた。すると双眸にぷっくりと盛り上がる涙、すぐにつぅ…と頬を伝う。
「好き…僕ずっとたいらくんが好き…。だからおかまでも良いんだ。」
洋の唇がそっと、僕の唇に触れた。僕は…目を閉じた。
「駄目…だよ…ひろし…」
そっと、身体を抱き締める。
僕は知っている。洋が僕のこと、好きなわけない。
洋の憧れの先は、いつだって兄の太一。勉強が出来て、スポーツが出来て、相談に乗ってくれて、頼り甲斐があって、男にも女にも人気がある。
それに比べて僕はただ、喧嘩が強いくらいだけだからな。勉強だって平均しか出来ない、全てが平均…。
僕は洋が可愛くて仕方ない。大事に、大事に守ってきた洋…。
だけどそれは『恋』とは違う。ただの『家族愛』であるはずなのだ。
「洋、お前が憧れていたのはにいちゃんだろ?太一だろ?」
するとフルフル…と首を振る。
「ヘンなおじさんが夢に出てくるようになって気付いたんだ。僕たいらくんが好き。たいらくんに触って欲しいんだ、ここも、ここも…」
そう言って僕の手を胸と股間に導く。
「男同士で性交渉なんか出来ない。」
僕には知識が無かった。気持ちはあったけど洋とセックス…なんて思ったことも無かった。
いつか、洋が女の子と恋に落ちて関係を結ぶ…ってことは想像していた、それで嫌悪を感じたけど、僕がどうにかしたいなんて思わなかった。
「蜜佐波…ヘンなおじさんはどんなふうに洋を抱いたんだ?」
洋が必死に説明すればするほど、沸沸と胸に湧きあがるジェラシー。
どうして弟にこんな感情を抱くのか分らない、だけど…。
「洋…」
「…おはよう、平。」
翌朝、洋は何事も無かったかのように家のダイニングに居た。
僕も出来るだけ平静を装っていた。
父と母は何も知らない。
昨日、僕は洋を抱いた。夢現でいる、洋を抱いた。何度も何度も洋は僕の名を呼んだ、僕もまた洋の名を囁いた。
そのまま洋は眠ってしまった。
目覚めた時にはいつもの洋に戻っていた。ちょっと照れくさそうに笑ったから
「どうした?」
って聞いたら、
「良い夢を見た」
って言った。
暫くして兄がアパートに戻って来た。
「蜜佐波が捕まった。」
と言ったけどどうして捕まったかは言わなかった。ただ、兄の左腕に巻かれた包帯が凄く気になったけど、兄はニッコリ微笑んで「なんでも無い」とだけ言った。
一番先に父が出掛ける、母はそれを見送る。
ダイニングには僕と洋。
「平?」
「ん?」
「ずっと、守ってくれる?これからも、守ってくれる?僕は弱いから、何かあったら守ってくれる?」
「洋…」
「平がいたから、僕は戻ってきた。平が守ってくれるって言ったから戻ってきた。」
僕は俯いて目を閉じた。
「にいちゃんが、洋を守ったんだよ、僕はなにもしていない、ただ…」
欲望のまま、洋を抱いただけ。
「平が好き。」
僕は黙って首を振る。
「洋に、僕は相応しくない。」
「だったら、相応しくなって、僕を守って。先生に犯されている間、僕は平を思っていた。無意識のうちに平が僕に勇気をくれた、『負けるな』って。もう誰にも触れ
られたくない、平だけ思って生きたい。」
素早く唇を重ねに来た。
「どうして僕が童貞だったか、やっと分かった。女の子に興味が無かったわけじゃない、だけど教師に強姦されておかまにされて…」
「洋、まだ間に合うんだから、恋しろよ。」
「うん…僕さ、ちょっと先生に感謝している。僕は平が好きだって気付かせてくれたから。ずっと好きだったんだ、だけどそんなこと考えもしなくって…バカみたいだ。」
「ちょっ…待て…」
僕は頭が動転していた。だって洋が僕のことを好きだって言っている。
「好きって…」
「平の恋人にして。」
…なに?…
「じゃあ平、どうして僕のこと抱いたの?興味本位?」
「違…う…」
だけど、恋じゃない…
玄関のドアが閉まる音がした。洋はカバンを持って立ち上がった。
「とりあえず、夜までに考えておいて。」
「あぁ…」
考えるって言ったって、なぁ…。
「ただいま」
今日はバイトがあって、僕はヘトヘトに疲れて家に戻った。兎に角、風呂に入って眠りたかった。
重い足を引きずって階段を上がり、自室のドアを開ける。タンスに手を掛け、下着を弄り出し、再びドアを閉めた。
「平。」
暗闇の中、洋が僕の姿をじっと見つめていた。実際には暗くて見えなかったけど、多分洋は僕を見つめている。
「洋…いいよ、僕のものにしてやる。」
「本当に?ずっと一緒にいてくれる?」
「あぁ。」
頭をポンポンと叩いて僕は階段を降りた。
僕は昼間、自分の大学の医学部へ足を運んだ。そこで精神科関係の本を探して読んでみた。
医学部の教授にも無理を言って話を聞いた。
その結果、出た答えは「洋は壊れている」と言うことだった。
僕が拒絶すればきっとまた、新しい狂気の世界へと移り住んで行くのだ。
だけど僕に洋を守りきれるだろうか?
気が重い、だけど約束したから、洋を守ってやるって約束したから…。
その晩から僕は洋と一緒のベッドで眠る様になった。
|
※珍しく、自作解説など。
前編と後編で主人公が交代しています。
だって自ら精神を壊してしまった洋にはお話を進行させることが出来なくなってしまったので。
夏っぽくミステリー仕立てにしたかったのになぁ〜。 |
 |