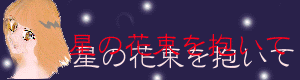どんなときでも 「ずるい…絶対にずるいよね?」
今日何回この言葉を口にしただろう。
だけどどうしても言わずにはいられなかった。
みかんを胸に抱き、僕はリビングのソファーで大きなため息をついた。
「どうして僕だけ留守番なんだろう…」
聖の小学校は新学期を迎えてすぐに運動会を開催する。今日はその当日だ。
「僕だって行きたかったのに。」
会場には零が行っている。本当は僕も行くはずだったんだ。だって僕は聖の親となる資格を得たのだから。…法的には無理だけど。
それでも零と一緒に聖の応援がしたかったんだ。
なのに…。
案の定、昨晩ママから電話が入った。
『明日、聖の運動会なんだって?』
ハンズフリーにしたスピーカーから聞こえたのはいきなりの怒声。
「どうして知っているんだよ。」
零はぶっきらぼうに答える。
『町内会の掲示板に貼ってあったもの。』
余計なことを…と内心思ったものの、聖が描いたポスターが駅に貼ってあったのを思い出して仕方が無いと諦めたのだった。
『お弁当、準備してあるからね。』
「ちょっと、待って?」
僕の準備してあるサンドイッチの材料は無駄になるの?
『何よ?陸は私の楽しみを奪おうって言うの?親権は渡さないからね。』
又だよ。
この間の結婚式からこっち、ずっとママの言い分はこれだ。確かに今、聖の親権は涼さんとママになっている。
『戸籍だって私と涼ちゃんの三男になっているんだから。絶対に零の養子になんかさせないんだからね。』
「分かったよ、運動会のお弁当が作りたいんだろう?作っていいから。」
えっ?
『本当に?だったらちょっとだけ考える。』
途端に声のトーンが変わると、さっさと電話を切った。
「言いたいことがあるなら直接来て言えばいいのに。」
一気に力が抜けてリビングの床に座り込んでしまった。
「陸をからかって喜んでいるんだよ。」
僕の肩をポンポンと叩いて、ソファに腰を下ろした。
「折角買ってきたのに無駄になっちゃったね。」
「朝ご飯にするからいいよ。」
仕事の帰りに、零と一緒にスーパーに立ち寄って買ってきたトマトときゅうり、レタスにスモークサーモン。ジャガイモにハム、苺にリンゴにキウイフルーツ、ツナ缶にコンビーフ缶、ベーコン、卵、サンドイッチ用に切ってもらった焼きたての食パンとバターロール…。ぜーんぶ、無駄になっちゃった。
でもその時点では、僕だって一緒に行く気満々だったんだ。なのに…。
「陸…あのね…今年から運動会に出られる父兄は三人までになっちゃったの。」
聖が寂しそうに俯いた。
「零にママに僕。大丈夫じゃない?」
「あきらちゃんが来るんだったら、涼ちゃんも当然来るだろう?」
「え…」
そうしたら、必然的に外されるのは僕。
「…そっか…そうだよね。親子水入らずで行ってくればいいよ、うん。」
膝を抱えて、精一杯明るい声を出したつもりだった。
だけど溢れる感情は抑えきれなくて、嗚咽が漏れた。
「そんなに、行きたかったんだ。いいよ、陸が行ってきて。僕は留守番…」
「駄目。」
違う、その場所に僕の居場所は無いんだ。
「やっぱり、聖のパパとママは涼さんとあきらママ…だから。僕は行かないほうがいい。」
聖が僕の隣に来て一緒に床に座った。
「僕ね、陸に応援して欲しくて一生懸命リレーの練習したよ。だから絶対に一番になれるよう、頑張る。」
応援、したい。
「パパとママが一生懸命応援してくれる。だから頑張って。」
「陸ぅ…」
聖の身体を抱きしめる。
「僕はここで待っている。聖が一番になるよう、祈っている。」
結婚式の日、パパに言われた。
『二人の結婚を祝福してくれる人もいるけど好奇の目で見る人だって当然いる。今日のところは陸のその格好だけで満足して帰ったけど、何かのネタを見つけたら次は絶対にスクープ記事にするはずだ。だから、ボロはだすな。絶対に周囲にかぎつけられるな。聖君が可愛いなら、彼がせめて18歳になるまでは二人の関係がどういうものかという証拠を見せずにトップを走ることだ。』
二人で聖の運動会に行ったらいけなかったんだよ。ママは、それを教えてくれたんだよね。
…だけど…。
「ずるいなぁ…可愛いだろうなぁ…いいなぁ…」
やっぱり愚痴ばかり口をついてしまう。
帰ってきたら一杯話を聞くんだ。夜中になってもいいから、聖から話を聞くんだ。
「でね、他の男の子はみんなプルーの花を手につけて踊っているのに、聖だけピンクなのよ。それがとっても可愛いんだけどね。ほらほら、この写真、見て見て。」
ママ…僕は今、ママに殺意すら覚えています。
聖は帰ってくるなりベッドに倒れこんでしまって、零は涼さんとなんだか知らないけど買い物があるとか言って出掛けてしまった。
置き去りにされた僕とママ。
ママは嬉々としてデジカメをパソコンに繋ぐと時系列で説明を始めた。
「ビデオもあるけど車の中に置いてきちゃった。」
「…もう、いい。」
「ん?それでね、リレーでね…」
「ママ、お願いだからそれ以上話さないで。僕は聖から聞きたいんだ。聖がどれだけ一生懸命頑張ったのか、聖から聞きたいんだ。」
「だから、すっごく頑張っていたんだから。全部でいち、に、三人抜いてね…」
「いい加減にして。」
僕はその場で立ち上がった。
「黙っててって言っているのが分からないの?僕は聖と話がしたいんだよ。ママに聞きたいことじゃない。」
「…渡さないから。聖は私の子なんだから。ちゃんと覚えているもの。私が聖を生んだのよ?」
「分かってる、そんなこと。僕には零の子は生めないからね。感謝しています。」
やばい。いけないこと、言った。
「ごめん、なさい。」
ママの表情は変化が無かった。
「…おかしい?零の子供を生んだら、おかしい?そうよね…やっぱり私、おかしいのよね?」
「そんなこと言っているんじゃない、僕はただ、聖から今日どれだけ頑張ったか聞きたかっただけで、ママがいけないなんて言っていないじゃないか。」
ママの顔がぐっと上を向いたかと思うと、僕を睨みつけた。
「いつから・・・そんなに生意気な子になっちゃったのよ。昔はとっても可愛かったのに。」
ポロポロポロポロ・・・ママの瞳からは涙が零れた。
ママは…時を止めていた分心も純粋なままで止まっていたんだ。だから全てのことが突然起こった出来事のように思えてしまうんだ、多分。
「あのね、僕はもう20歳になったんだよ?子供じゃない。わかる?」
涙でぐちゃぐちゃな顔のまま、僕をじっと見つめる。
「そう、なのよね。ちっちゃかったのに。抱きしめてもじたばたと苦しがっていたのに。今ではびくともしない。あの頃は女の子になるんじゃないかって、とっても楽しみにしていたのにやっぱり男の子として育っているし。だけど零のこと好きだなんて言うし…聖の親になりたいなんて…どうかしているのよ、絶対。」
床にペタンとお尻を着いて座ると、大きくため息をついた。
「聖を、零の養子にしても良いって涼が言うの。二人の結婚祝いに聖をあげるって言うのよ?聖は、物じゃない。私達の可愛い子供。零だって陸だって私の可愛い子供。…もう少しだけ、私の子供で居て欲しいの。」
ママ。寂しいの?涼さんと仲良く暮らしているのに、寂しいの?
僕はママを抱きしめた。
「生意気。やっぱり陸は生意気よ。私、最近陸を見るとドキドキするの。一人の男になりつつあるの。そんなあなたが可愛くて仕方ない。」
ママの腕が僕の背中を捉えて強く、抱きしめ返してきた。
「私の、陸。」
ママにとって、零も、聖も、実紅ちゃんも夾ちゃんもそして僕も、みんな生まれたての子供と一緒なんだね。どんなに大きくなっても、子供のまま。自立していなくなってしまうのが寂しいんだね。
「零はいつも陸のことばかり話していたから、大好きなんだなって思っていたの。陸の視線はいつだって零を探していたから大好きなんだなって、思ったの。二人が一緒にいるのは当然のことだって、私は思ったのよ。実紅は…一人の人を追い続けていた。だけどそれが破れて傷ついた時に、私が傷つけた裕ちゃんに助けてもらったんだってね。だから家にいなくても…いられなくても仕方ないと思ったの。夾は、無口で引っ込み思案だから涼には分からなかったみたいなんだけど、あの子はパパが大好きなの。私にくっついていればパパと話ができるから、だから私のそばにいるのよ。零みたいに同じ道を歩まずに、一番近くにいられる方法を選んだ。聖は…わからない。私の記憶の中に聖がいないの。だからこれから一杯思い出を残したいの。分かってくれる?」
うん…肩口で頷くことで肯定した。
「あー、ずるーい。」
昼寝から覚めた聖が、僕達を見つけて飛んできた。
ママが嬉しそうに僕から離れて聖を抱き寄せようと両手を広げると…
「陸ぅ〜僕ね、リレーで四人抜いたんだよ。」
そう言って僕の腕の中に飛び込んできたのだった。
「やっぱり陸嫌いっ」
ママは不機嫌になって立ち上がった。
聖は何がなんだかわからないという表情で、僕を見た。
僕は。ただ笑っていた。
「涼さんと何の話だったの?」
夕食が済んで二人が帰り、聖もお風呂から上がると疲れからかさっさと寝てしまい、リビングには零と僕の二人だけになった。
「聖のこと。あきらちゃんが嫌がっているんだってさ、聖の親権手放すの。」
「うん、さっき聞いた。涼さんは何だって?」
「親権っていうのは両親が持つものなんだよ。だから養子縁組しないと僕には移ってこないんだよね。兄弟でも養子縁組は出来るんだけど、理由がないんだよ。大抵の場合、資産があって子供がいないから財産を残すために養子縁組するんだけど、僕の場合まだ結婚の余地があるだろう?財産は無いし…。」
「不能…ってことにすればいいじゃないか。大体役所に提出するのに理由がいるの?」
僕は何故だかイライラしていた。
「15歳未満だから家庭裁判所に行かないといけないんだ。それに…無理してあきらちゃんから聖を引き離さなくても良いんじゃないかって、そう思ったんだ。聖は僕達の子だって、それだけで良いんじゃないかって思うんだよ。」
…ママに、味方するんだ。
聖の親権なんて、20歳になったら失効するんだし、本当はそんなに拘っているわけじゃない。家庭裁判所に行ってまでわざわざすることでもないと思う。無責任かもしれないけど、僕は三人でいられればそれでいい。
だけどね、聖はそれでいいのだろうか?
「…聖の親権、どうやってもあきらちゃんからは動かせないんだ。…陸の出生届ってどうやって出したんだろう?あきらちゃんは病院で産んだんだろう?陸のこと。だけど母親はいないことになっている。」
「いるよ。僕の母親、ちゃんといるんだ。」
零には黙っていたけど。パパもずっと僕には教えてくれなかったけど。
「ママは僕のこと、皆とは違う病院で産んだんだ。パパの知り合いの人。でね、パパにお姉さんがいるの知ってる?早くにお嫁に行っちゃったから、ママもそんなに知らなかったみたいなんだ。ママが病院に行く日は、いつもおばちゃんが来ててね、一緒に診察室に入るんだって。」
「肩代わり?」
「うん」
僕はおばちゃんちの子供ってことになっている。パパは僕が生まれて直ぐに養子縁組したんだ。けど僕が子供の時にはじいちゃんとばあちゃんが親代わりで、近所の人も兄弟たって信じていた。誰も真相には触れなかったってことらしいんだ。
「あきらちゃんは妊娠していなかったことになっているのか。全て、記録はその伯母さんのものとなっているんだ?医師がぐるにならなれば出来ないよな…」
こくん。
「聖の時にはそんなこと考えもしなかった。裕二さんは本当に考えて考え抜いてチャンスを狙っていたんだ。」
「ママのこと、愛していたんだって。」
なんか、違う気がするけどね。
「分かったとき、あきらちゃんが妊娠したって分かった時、僕は逃げたんだ。涼ちゃんに全て押し付けて、逃げた。だって自分の母親を妊娠させたなんて…言えない。どうやって病院に連れて行けば良かったんだ?書類にサインしておろせば良かった?」
零?
「僕は、許されない恋ばかりしている。あきらちゃんに恋した。陸に恋した。聖を授かったのは戒めなんだと思う。」
「なんで?聖は可愛いのに?そんなに辛い?僕と一緒に歩いていくのは辛い?」
フルフルと首を振る。僕は零の前に座ってその顔を見上げる。
「もしかしていつも苦しんでいた?僕と一緒にいること、聖を引き取ったこと、苦しんでいた?だったらごめんね。僕考えなしで、いつだって自分か一番嬉しいことだけしたいって思っているから、零を苦しめていたかもしれない。僕はままごとみたいな感覚でいたからね。」
零の腕が僕の身体を抱き上げるようにして背中に回された。
「違う、それは違う。陸を、愛している。だから一緒にいたい。それはわかっている。だけどどうして許してもらえないんだ?聖は…我慢できるんだ。僕の中で聖の事は諦められるんだ。涼ちゃんとあきらちゃんがついていてくれれば、僕は不要だってこと、分かっているし当然だって思う。だけど陸のことは諦められない。どうしてコソコソとしなきゃいけない?堂々と太陽の下を歩きたい。…こんな仕事、選ばなければ良かった。」
抱き寄せていた腕を放し、両手で顔を覆って苦しそうな声を発していた。
「サラリーマンでも、同じだよ?…前に一人で電車に乗っていたとき、背広を着た男の人が二人、手を繋いで来たらね、女子高生が『あっ、ホモだ』って言って指差すんだ。その二人は慌てて手を放しちゃってそれっきり気まずそうにしていた。堂々としたくても世の中の好奇は集中するんだ。無理なんだよ。ねぇ…いつか、僕達がそんな世の中を変えられたらいいと思わない?そのために僕達はステージに立っているんだ。そのために僕達は結婚したんだ、違う?」
今日の零はなぜか弱気だ。時々こんな日がある。
「僕は無力だ。今日だって陸を連れて行くことが出来なかった。自分の欲望ばかり陸にぶつけて、そのくせ守ってやるなんて言いながらちっとも希望を適えてあげられない。」
再び抱き寄せられ、耳元で低くうめく声がした。
「弱虫で、ごめん。だけど、陸が必要なんだ。こんな僕だけど、支えて欲しい。必ず、守るから。なにがあっても守ってあげるから。」
「前に言ったでしょ?守ってくれなくてもいい。僕は自分で歩ける。僕達が守るのは聖だよ?聖が大人になるまでは一生懸命頑張ろうね。」
零は、大きなプレッシャーと戦っているんだ。
「聖のこと、今はこのままでいいと思う。成人したらきっと分かってくれるから。」
でもまだまだ先の話。僕だってやっと二十歳になったばかりだしね。
僕達は自分達の形で幸せになれればいいと思う。何が正しくて何が間違っているか、そんなのわからない。
世間の常識も、どれが本当に道徳的な常識で、どれが非道徳的な常識かが分からなくなっている今、もう一度考え直したらいいことが沢山あると思う。
「二十年くらいしたら、政治家になろうかな…」
僕が呟くと零は無言で頷いた。
「僕が、世の中を変えられたらいいけどな…剛志くんも誘ってみようかな…」
何故だかその時、剛志くんなら一緒に頑張ってくれるような気がした。
「僕も着いて行きますっ」
翌日、何気なく二十年後の構想?を話していたら、賛同してくれたのは斉木くんだった。
当然、僕は斉木くんの腕の中…。暫く後に斉木くんが苦痛の叫びを上げたのは内緒。
資料参考
誰も教えてくれない戸籍の話
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dare.sinken.html